2010年01月13日(水)
|
【EOS7D EOS5D 動画】だった。動画が上がっていなくて申し訳ない。 EOS7DとEOS5DにFマウントのAiニッコールを使う場合、EOS7DはAPS-Cサイズ、EOS5Dは35㎜フルサイズとなるが、フルサイズ用のレンズをAPS-CやニコンのDXフォーマットに使用する場合は注意が必要だ。 イメージサークルの大きいフルサイズ用のレンズをAPS-CやDXといった撮像面積が小さいハーフ版デジタル一眼レフに使用すると画角外の余分な光線が鏡筒内面やレンズ側面、またカメラのミラーボックス内部で不要に反射してフレアーを起こす。フレアーは特に暗部に大きく影響する。 動画を撮る場合やスタジオではマットボックスや蛇腹フードを用いて画角外の光線をカットする。時に開放では口径食を起してしまうギリギリのところまで攻めたりもする。しかし、いつもいつも蛇腹フードを使うわけには行かない。邪魔になるからだ。大方の人はメーカー純正のスナップオンやバヨネット式の花形フードを使われていると思う。しかしフルサイズ用レンズの場合はメーカー純正ではハーフ版カメラで使用した場合は浅すぎる。      私が大好きなAi Zoom Nikkor ED 50-300mm F4.5やAi-sのAi Zoom Nikkor ED 50-300mm F4.5Sでは純正は95Φのカブセ式フードHK-5になる。   最後の写真はDXフォーマットで使用するためにフードを装着したオールドニッコールレンズだ。  APS-Cで使用すると25-50mmは40-80mm、20㎜は32㎜、58-11mm相当の焦点距離にシフトする。フィルムカメラの使用が長かったので、APS-CやDXモードの時はオリンパスペンFを使っていた時の頃を思い出して使うのだが、なかなか画角がイメージできない。また撮影時に1.6倍や1.5倍をかけて計算するよりも換算表の方が便利が良いし、レンズに換算焦点距離を印刷したテプラを貼ったりしている。 古いレンズの場合、別売りや付属のフード類はメーカーに在庫は無く、Yahoo!やe-Bay、または田舎の中古カメラ店を探すと格安で入手できる場合がある。間違っても都会の中古カメラ店などで購入することは避けたい。時に発売当時の数倍のプレミア商品になっていたりするからだ。購入や入札する場合は事前に発売当時の定価は調べておきたいところだ。以前四国の中古カメラ店で500円で購入したものと同型のものが大阪のカメラ店で1万円を越える金額で販売されていた。 安く販売されていたときは迷わず衝動買いをお薦めする。見逃して次に入手できるチャンスはいつ訪れるかはわからない。 |
2010年01月10日(日)
|
ニコンのAF-S Nikkor 14-24mm f/2.8G EDを検討するためレビューを探していた。特に歪曲収差がどうなのかが気になる。 見つけたサイトはhttp://www.photoreview.com.au/Nikon/reviews/cameraaccessories/afs-nikkor-1424mm-f28g-ed-lens.aspx オーストラリアのサイトだが、実写が載っていた。 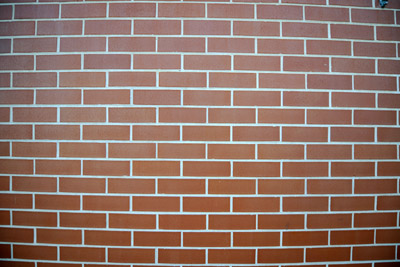 14mm setting at f/2.8. 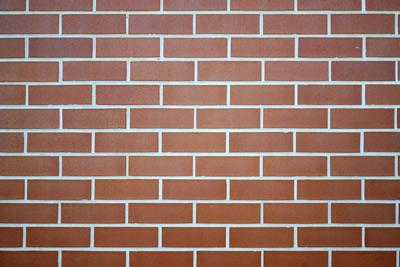 24mm setting at f/2.8. そこでもう一つ調べてみた。AF-S Nikkor 24-70mm f/2.8G EDだ。同じくPhotoreviewの画像だ。 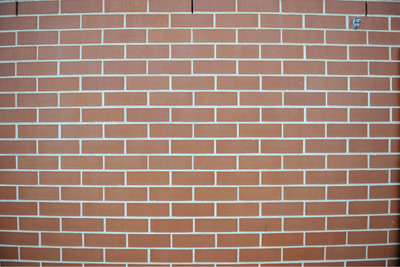 24mm setting at f/2.8. 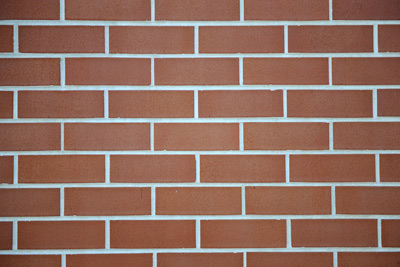 70mm setting at f/2.8. このレンズもワイド端の画像は酷すぎる。ともに20万以上する高級レンズなのだが・・・・ これまでにニコンの広角ズームは学生時代に28-45㎜F4.5をニコンFやF2で使ってきた。そしてF3Pでは25-50㎜F4、35-70㎜F3.5を使ってきた。全てフィルム時代のものだが、これほどまでに湾曲することは無かった。25-50㎜F4、35-70㎜F3.5はともにアタッチメントサイズ72Φのマニュアルフォーカスのもだが、現在もD700で使用している。 レビューの結果を見る限りは進化というよりも退化しているとさえ見受けてしまう。 ふと思ったのだが、デジタル一眼レフが流行したのには高倍率ズームがあるからのようだが、デジタル現像の際に歪曲収差や倍率色収差が補正できるためにメーカーは解像度に的を絞ってレンズ設計しているのだろうか?あくまで私の想像だが、全く外れているとは言えないと思う。しかしこの湾曲はムービー撮影では致命的だ。デジタル一眼レフの動画形式はMPEG-4やAVIだが、編集時に歪曲収差の補正をするには無理がある。やはり結像時点で歪曲収差が残らないようにしてもらいたい。 それにしてもよく曲がるレンズたちである。 |
2010年01月01日(金)
|
明けましておめでとうございます。 旧年中は勝手気ままなブログにお付き合いくださり有難うございました。今年も相変わらず独断と偏見に満ちたブログになること必至ですが、何卒お引き立てのほどお願い申し上げます。 笹邊幸人 2010年元旦 昨年から徐々に計画していたEOS動画がようやくスタートラインに立った。まだ仕事を請けるところまでは完成していないが、その一部を紹介するためにスタジオで機材の撮影を行った。  次の写真は最短焦点距離のAi Nikkor 15mm F3.5Sだ。  先ほど書いたEOS+ニッコールレンズのことだが、EFレンズには絞り環が無く、ボディー側から電気的にコントロールするようになっている。同様にニコンも最新のレンズはキヤノン同様絞り環が省かれてしまった。実はこれが動画撮影にとって非常に不便になる。ビデオカメラの絞り(アイリス)は連続可変し、作画意図に合わせて微妙なコントロールが可能(一部民生機のVXやPDなどでは段階変化)である。中継録画のようにVEが撮影中にアイリスを調整することはないが、時にアイリスフォローが必要な場合は段階変化はいただけない。 では、何故ニッコールにキヤノンなのか? それはニコンのムービー機能が動画制作向けのものではなく「連続する静止画」としての要望からスタートしたらしく、ファインダーがアイリスの変化に対応して変化しないようになっているからだ。D3sで色々確認したがアイリスを絞ってもライブビューは明るいままだった。メニューで変更できるのかとニコンの技術者にも聞いたが無理なようだ。ニコンはあくまで写真機ということだ。 我々は普段からソニーのビデオカメラにキヤノンやフジノンのレンズを装着して使っているため、ビデオカメラにカメラメーカー純正のレンズを装着する必要は感じていないしビデオカメラメーカーもOEMで純正レンズを供給している程度だ。 EOS動画を考えた時にレンズは迷わずマニュアルフォーカスのニッコールと考えていた。もちろんNIKON FからF2、F3Pと使ってきたユーザーゆえにニッコールへの愛着は強い。もちろんキヤノンF1やA1も使い、FDレンズも色々使ってきたが、ここに来てEOSのマウントに余分な光学系を入れないで使えるFマウントのMFニッコールレンズが輝きだした。当然余分なコストがかからないこともEOS+ニッコールレンズの大きな理由だ。キヤノンのEFレンズもEF-S17-55mm F2.8ISやEF70-200mm F2.8Lを持っているが、これを5DMkⅡに装着して写真を取るかと言えば疑問だ。写真はあくまでD700である。 EOS+ニッコールレンズに対する基本的な考え方は5DMkⅡはあくまで撮像部分である。そのためにメーカー保証の対象から外れる改造なども必要だ。この考え方はビデオカメラに置き換えるとわかりやすい。ビデオカメラの場合はレンズ、カメラヘッド、ファインダー、マイクなど全てがバラバラに構成され、必要に応じてメーカーの枠を越えてシステムを構築する。EOS動画も同様、必要に応じてレンズ、周辺機器などを組み合わせていくことが動画カメラとしては自然な流れではないだろうか。写真には全貌は写っていないが、5DMkⅡに取り付けられたモニターは5.6吋の液晶モニター。小柄だが1024×600の解像度を持ち、EOS5DmkⅡとはHDMIで接続する。電源はソニーのNP-F970を12Vに昇圧して使用している。 際最後の写真はAi AF Zoom Micro Nikkor ED 70-180mm F4.5-5.6Dを装着したEOS5DmkⅡ  |
2009年11月24日(火)
|
キヤノンダイアル35というキーワードが多い。検索していただいた方々に古いコンテンツのままでは申し訳ないので新しいスライドショーを作った。ダイアル35はたぶんニコンF3Pなどよりも好きなカメラになるとおもう。 最近のフルオートカメラに比べると決して押すだけでは写らないが、ネガカラーを詰めて現像と同時のデータ化を行えばデジカメと同じ感覚で使え、何よりも現像上がりにワクワク出来る。完全に趣味の世界だ。 下のスライドショーは昨夜スタジオで簡単に取ってみたもの。明かりに時間をさけなかったので細部に不満はあるが、あまりネットで見かけない部分アップを中心に撮ってみた。このブログにはI FRAMEで埋め込んでいる。※FireFox、Opera、Safariでは問題なく再生できるが、IE-8及びSleipnirでは表示されない場合がある。その場合はコチラのページで再生していただきたい。 もしもキヤノンがダイアル35のデザインのままAPC-C(ハーフ版サイズ)のデジカメを作ってくれれば・・・・・背面の感度換算表が液晶に変わり、レンズ周辺のCDS受光部はフラッシュに・・・・ゼンマイモーター部にはもちろんバッテリー。期待してしまうのは私だけではないと思う。名称はCANON Didital 35だろうか。 |
2009年11月19日(木)
「ニコンF3P」でヒットしていた。デジタル化したためにまず使うことが無くなったカメラだ。 |
2009年11月08日(日)
インド ハイデラバードというキーワードだった。かなり前にスライドショーを掲載したページが1番上にヒットしていた。そのお陰か、最近インドの映像制作&コーディネートの会社からメールが来た。その中には実績も書かれていた。
主な業務実績 NHK、日本テレビ、テレビ東京 TBS、、テレビ朝日、キューピー、北海道新聞、BS1地球アゴラ、テレビユニオン、NTV、フイルム ガーデン(オーストラリア)、電通、メディア・オーパス、Dancyu雑誌、S.P.LiveCo.Ltd.Tokyo、J-POWER、JR東など 石原都知事がインドに訪問された際にはすべてのコーディネートをさせて頂き、ウルルン滞在記も何度か携りました。 |
2009年10月30日(金)
「琵琶湖 鮎 産卵 死骸」というキーワードがあった。 ところが九月半ばを過ぎると川は一変する。  今琵琶湖はビワマス産卵の時期だが、鮎に比べるとビワマスは個体数が少ないためのにこういった匂いに会うことは少ない。 |
2009年10月27日(火)
HDまめカム 水中という検索。検索されていたページは「SONY 豆カムHDを用いたBoomCamシステムのご案内」というページ。紹介している豆カムHDは水中撮影だけではなくVPなどでハイアングルやクレーンショットにも使用している。HDVのHVR-Z5Jと並んで活躍してくれる機材になっている。    他にもSUNRUN POLEという手軽なものも作っている。アルミパイプに豆カムヘッド、レコーダー、水準器などをつけたポールだ。非常に軽量で、誰にでも手軽に操作できる。 先日琵琶湖博物館主催の催しで船上から撮った映像をYouTubeにアップしている。 なお、この日の様子をFieldReportに写真を添えて掲載している。 http://svs.ne.jp/cgi-diary/ 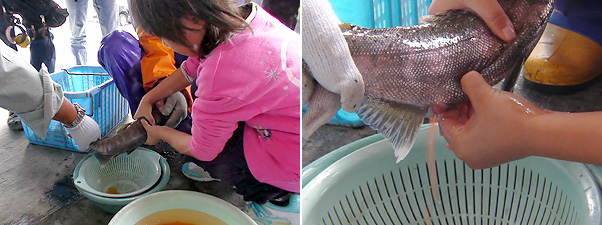  ちなみにこれらの写真は全て豆カムHDで撮影したものだ。ヘッドとモニター、操作部が分離していることで、普通のカメラとは違った撮り方も出来そうだ。もちろん画質はデジ一とは比べるべきではないが、写真機能は1920×1080のハイビジョンだけではなく、写真モードにすることで2034×1728ピクセルのJPEGを撮ることが出来る。意外と便利なものである。 今回の検索でヒットしていページにエルグベンチャーのサイトがあった。そこにまめカム「水中撮影パッケージ」発売予定。お問い合せ受付中です!とある。 写真の中に豆カム用の中に「カメラ・モノポッド」が有った。一脚ベースのもののようだが水中撮影パッケージというからには耐蝕性に優れたものに違いない。 機材メーカーが参入してくることで、ソニーの豆カムのみならず、パナの豆カム?も含めて面白くなりそうだ。 |
2009年02月22日(日)
愛用のCybershot T9だが、来月飛躍的に進化したDSC-T900とDSC-T90が発売される。注目はT900だ。  店頭予想価格はHD再生スタンドが付属して45,000円程だそうだ。 動画は1280×720のハイビジョンだがソニーの動画としては珍しくプログレッシブである。2枚で1フレームを構成するインターレースと違い、1枚で完結する。動画はその静止画が連続しているということである。 豆カムHDも凄いが、このDSC-T900、メモカメラというにはあまりに勿体無い。物欲が目を覚ましそうな近日発売のCybershot DSC-T900である。 |
2009年2月22日
| 記事へ |
コメント(0) |
トラックバック(0) |
| 映像制作・撮影技術 / 写真撮影・カメラ機材 |
トラックバックURL:http://blog.zaq.ne.jp/senri/trackback/824/
※ブログ管理者が承認するまで表示されません
| 映像制作・撮影技術 / 写真撮影・カメラ機材 |
トラックバックURL:http://blog.zaq.ne.jp/senri/trackback/824/
※ブログ管理者が承認するまで表示されません
2008年12月13日(土)
|
ビデオ 静止画 サービス 大阪だった。以前のVHSやHi-8時代に比べるとDVやHDVやDVDが普及した今日では静止画としての用途も多くなった。特にWEBやパワーポイントに貼り付ける用途である。もちろん画質的にはデジカメには及ばないものの、毎秒30~60枚の静止画で構成される動画では容易く決定的瞬間をものにすることが可能だ。 コンピューターに取り込んだ動画や直接DVDから静止画(BMP/TIFF)を書き出す作業である。下はJVCのHDVカムコーダーHD250で撮影(720/60P)した動画から取り出した新世界の静止画だ。写真をクリックすると少し大きなサイズで表示される。(オリジナルは1280×720ピクセル) ビデオから取り出した写真と言えども、WEBやPPTで使うには十分なサイズと解像度を持っている。もちろんPSDデータでの出力も可能である。 |
2008年12月13日
| 記事へ |
コメント(0) |
トラックバック(0) |
| 映像制作・撮影技術 / 写真撮影・カメラ機材 / コンピュータ・IT系 |
トラックバックURL:http://blog.zaq.ne.jp/senri/trackback/797/
※ブログ管理者が承認するまで表示されません
| 映像制作・撮影技術 / 写真撮影・カメラ機材 / コンピュータ・IT系 |
トラックバックURL:http://blog.zaq.ne.jp/senri/trackback/797/
※ブログ管理者が承認するまで表示されません
2008年11月25日(火)
|
ネガフィルム→データ変換 ネガフィルムからのデータ変換は簡単だ。ラボにお願いするだけでよい。デジカメ一色の写真界だが、決してフィルムがなくなったわけではない。また今回の検索のようにネガの利用も便利だ。 写真は9月23日に神戸のオルビスホールで撮影した友人の宮内タカユキだ。私と同い年である。撮影はNikon F3Pに300mmF2.8+エクステンダーTC300を付けて撮影したものでフィルムはフジのNATURA 1600だ。 ブログでは大きな写真が表示できないので別ウインドウに大きなサイズを用意した。 仕事で撮影する場合は確実にデジタルを使用するが、宮内の撮影はフィルムに拘ってみた。 撮影したその場でポラを引くようにプレビューしてしまうデジカメでは現像が上がる楽しみもワクワクした気持ちも無くなってしまう。まして大判ではなく35mmSLRだからポラというのも似合わない。やはり前面マットのB型フォーカシングスクリーンで狙ったところにフォーカスを合わせたいのである。また、デジカメでステージを撮るとその液晶の明るさが周りの観客に多大な迷惑をかけることになる。もちろんデジタルSLRの液晶を切っておけば済む話だが、それならデジタルを使う理由が無い。 講釈はさておいて、要は宮内を撮るなら昔どおりの銀塩で撮ろう、というだけの理由だ。ただし昔と違う点は三脚だ。昔はジッツォやハスキーといった写真用の三脚を利用したが、今はビデオ用のビジョン3を使う。動きのある被写体ではビデオ用のヘッドの方が遥かに使いやすい。 話がそれたが、フジでネガフィルムをデータ化してもらうとCD-Rでインデックスが添付されて上がってくる。データサイズは1840×1232と、小さいサイズの597×400だ。WEBでの使用であれば十分なサイズだ。費用も同時スキャンであれば現像代+1000円ほどである。 デジカメユーザーの若い人も、デジカメに移行してしまった年配のデジカメファンも部屋の隅で眠っているマニュアルフォーカス銀塩SLRを引っ張り出してフィルムでの撮影を楽しんでみてはいかがだろうか。現像が上がるまでのワクワクした気分も楽しめるに違いない。 |
2008年11月25日
| 記事へ |
コメント(0) |
トラックバック(0) |
| 写真撮影・カメラ機材 / コンピュータ・IT系 / アーチスト・タレント |
トラックバックURL:http://blog.zaq.ne.jp/senri/trackback/788/
※ブログ管理者が承認するまで表示されません
| 写真撮影・カメラ機材 / コンピュータ・IT系 / アーチスト・タレント |
トラックバックURL:http://blog.zaq.ne.jp/senri/trackback/788/
※ブログ管理者が承認するまで表示されません
2008年09月30日(火)
|
「canon EOS 5DマークⅡ」「5dマークⅡ」共に今日の検索キーワードだ。特にcanon EOS 5DマークⅡではヤフーのかなり上位にヒットしていた。このブログに記事を書いたのは9月28日で、まだ2日しかたっていない。にもかかわらずこの結果はブロガリの検索エンジン効果ということになる。色々と不具合のあるZAQのブロガリだが、検索エンジンに好かれる要素を持っているのではないだろうか。 それにしても今日のヒット数は多かった。  さて、明日からは10月だ。ということは正月まで僅かということである。つい先日まで暑い暑いと思っていたところに急な寒波で、早朝の車では思わずヒーターに手が行ってしまう。友人の山小屋からの便りでは最低気温0℃ 最高気温15℃ということだ。そろそろ冬支度をしなければならない。・・・いや、ここは大阪、雪が降るまでにはまだ2ヶ月余りはある。その前にビワマスの撮影に行こう。そして正月の餅代を稼がなくては。 |
2008年9月30日
| 記事へ |
コメント(0) |
トラックバック(0) |
| 検索エンジン・SEO / 写真撮影・カメラ機材 / 自然環境・自然科学 |
トラックバックURL:http://blog.zaq.ne.jp/senri/trackback/739/
※ブログ管理者が承認するまで表示されません
| 検索エンジン・SEO / 写真撮影・カメラ機材 / 自然環境・自然科学 |
トラックバックURL:http://blog.zaq.ne.jp/senri/trackback/739/
※ブログ管理者が承認するまで表示されません
2008年09月29日(月)
|
デジカメネタが続いたついでにもう一発デジカメの話。 私の会社の写真担当が「オートフォーカスがイマイチ」と嘆いている。私は仕事柄マニュアルフォーカスで撮れるジャンルが担当なので、デジタルSLRでオートフォーカスを使うことは少ない。それどころか、ニコンD700のようにファインダーがしっかりしていて、旧のマニュアルフォーカスレンズが使えるデジタルSLRを好む。さらにフォーカシングスクリーンには必ず全面マットを選ぶ。つまり全面マットのスクリーンを選べる機種である。そしてレンズは28mmF2や35mmF1.4、135mmF2、300mmF2.8など。理由は簡単だ。明るいレンズでマット面でフォーカスを合わせるだけだ。 で、問題のAFデジタルSLRだが、AFについてはレンズごとに補正値を記憶できるらしい。そして前ピン、後ピンも微調整できるそうだ。 いったいどういうことなのだろうか。一眼レフならレンズの焦点=撮像面と、ミラーで反射してきた光を擬似的に合焦させるフォーカシングスクリーンは等価のはずで、これが違っていれば一眼レフとは言えない。ビューカメラでも同様だ。ピントガラスの合焦面とカットフィルムフォルダーのフィルム面が等価であることが条件だ。 ところが高級デジタル一眼レフレックスカメラはボディーとレンズに相性があったり・・・・・・それを微調整する機能をカメラ本体に持たせていたりする。一見いかにも高機能そうに見えつつ、実際は微調整作業をメーカーのサービスが放棄したこことではないだろうか。 最近のデジタルSLRのCM(WEBも含めて)はちょっと誇大というか、派手な気がする。デジタル一眼レフを形容するキャッチコピーを見る限り技術的に完璧を期したように見えるが、はたして今のデジカメのAF技術は頂点に達しているだろうか。オートフォーカスの究極は「人の眼」だ。合わせたいところに瞬時に合焦することだ。ところが、人間にとって何の苦労も無いこの作業が最新の技術をもってしても未だ中途半端な合焦をしてしまう。 「製品ごとに微調整を余儀なくされるオートフォーカスとは何ぞや」といいたい。レンズ交換の完全互換性があってこそSLRではないだろうか。これではオートフォーカス=AFではなく、オートニアフォーカス=ANFデジタルSLRではないだろうか。 話は違うが、ソニーのCMOSセンサーに対する公開資料には好感が持てる。その中のCMOSへの期待と未来ではCMOSに対する今後の取り組みも書かれている。製品の弱点をしっかりと見極めることが将来に結びつくものと期待している。 参考までに松下のP2専用小型HDカムコーダーの新製品HPX-175は撮像素子にプログレッシブCCDを使用している。年末に発売されるHVR-Z5Jと同価格帯の製品だが、この勝負、しっかりと見届けたい。  |
2008年9月29日
| 記事へ |
コメント(0) |
トラックバック(0) |
| 写真撮影・カメラ機材 |
トラックバックURL:http://blog.zaq.ne.jp/senri/trackback/737/
※ブログ管理者が承認するまで表示されません
| 写真撮影・カメラ機材 |
トラックバックURL:http://blog.zaq.ne.jp/senri/trackback/737/
※ブログ管理者が承認するまで表示されません
 では、HDCAMのブリンプはというと、「マチャアキ海を行く」で多くの人に親しまれた「後藤くん」の後藤アクアティックスが作るHDW-750用で水中ブリンプ本体:500万円~550万円だ。また、HVR-Z1J用でも100万以上になる。 少し安いところでもSea&Seaで50万、アンフィビコのものでも100万近い。 ところが今回発表されたEOS 5D マークⅡではどうだろう。  11月発売予定のEOS 5D マークⅡ、この新型デジタルSLRカメラが地上に限らず、水中から宇宙まで、一気に塗り替えてしまうかもしれない。願わくは動画撮影に特化したマニュアル機能の追加など、11月の発売までにはなんとか対応してもらいたいものだ。それこそThe Next HD Camcorderである。 |
2008年09月28日(日)
|
ある人からの情報。驚きである。 USAキヤノンにあるEOS 5D マークⅡの動画だ。 http://www.usa.canon.com/dlc/controller?act=GetArticleAct&articleID=2086 視聴にはQuicktime7が必要だが、見れば衝撃を受けること間違いなしだ。 This video was shot with a pre-production Canon EOS 5D Mark II digital SLR. The files used to create this video were not manipulated in any way, only re-compressed for ¼ resolution display on our website. To view Vincent Laforet’s comments and behind-the-scenes video on the making of REVERIE, please visit his blog: blog.vincentlaforet.com とあるように、発売前ののキヤノンEOS 5DマークIIデジタルの一眼レフで撮られたものだ。そしてヴィンセント・ラフォレのコメントとメイキングビデオが彼のブログに載っている。ブログで彼はEOS 5D マークⅡをhe next HD camcorderと書いているが、それはもうすぐそばまで来ている。EOS 5D マークⅡはキヤノンのHDカムコーダーXH A1などとは全く次元の異なる撮影マシーンであることは確かだ。 http://blog.vincentlaforet.com/2008/09/23/behind-the-scenes-video/#comment-2436 ここにきてデジタル一眼レフとデジタルシネマの境が曖昧になってきたように思う。撮影レンズの自由度ではデジタルSLRのEOSに軍配が上がることは勿論であり、フルサイズの撮像素子は35mm映画サイズよりも有利だ。 後はEOS 5D マークⅡのシューティングスタイルだけである。EOS 5D マークⅡをシネスタイルに改造するガレージメーカーも出てきそうな気がする。 D700も欲しいが、EOS 5D マークⅡも欲しくなってしまう。しかしそれよりもEOS 5D マークⅡの動画で撮らなければならない仕事が欲しい! ちなみに今日はある企業の50周年記念のパーティーの収録だ。オーダーのフォーマットはDVCAM SDの4:3である。放送以外のHD化にはまだしばらく時間がかかるのが現実のようだ。 |
2008年9月28日
| 記事へ |
コメント(9) |
トラックバック(1) |
| 映像制作・撮影技術 / 写真撮影・カメラ機材 / 備忘録・メモ書き |
トラックバックURL:http://blog.zaq.ne.jp/senri/trackback/735/
※ブログ管理者が承認するまで表示されません
| 映像制作・撮影技術 / 写真撮影・カメラ機材 / 備忘録・メモ書き |
トラックバックURL:http://blog.zaq.ne.jp/senri/trackback/735/
※ブログ管理者が承認するまで表示されません
| 前へ | 次へ |
PHOTOHITOブログパーツ
|
ニックネーム:SENRI 都道府県:関西・大阪府 映像制作/撮影技術会社 (株)千里ビデオサービス 代表取締役& 北八ヶ岳麦草ヒュッテHPの管理人です。よろしくお願いします。 ↓色々出ます↓ »くわしく見る バイオグラフィー |











