2007�N06��08��(��)
|
�@�uHDV Vision 3�v�ł���B�r�W����3�Ƃ͉p���̃r���e�������Vision�V���[�Y�̃r�f�I�p�O�r�ōł������L�������T�|�[�g�̂��Ƃ��B���̉�Ђł͎��Vision 10�A11�A100���g�p���A����40�{�N���X�̖]�������Y���g�p����ꍇ��Vision 20�Ȃǂ��g�p���Ă���B�������������̂ɔ�ׂ��Vision 3�͉��i��20���]��Ɣj�i�̉��i�ݒ�ɂȂ��Ă���B���̉��i�ݒ�̔w�i�ɂ̓}���t���b�g�Ђ�OEM�ƌ����b���L�邪�A�}���t���b�g�Ƃ͂��Ȃ����Ă���B���Ȃ݂Ƀt�����X���̃W�b�c�IG-1380���ł͓h�F�����W�b�c�I�����}���t���b�g��#505�ƑS���������̂��BVision 3�͍\���������Ă��邪�A�J�E���^�[�o�����X�\����505��1380�Ƃ͈قȂ�X�v�����O�������Ɏ��t�����Ă���B�����ăN�C�b�N�v���[�g���r�W�����V���[�Y�Ɠ������̂��g���Ă���B����Ƀu���[�L�̍\���͏�ʋ@���Vision 6��8�A11�ȂǂƓ����\���ɂȂ��Ă��āA�y���g���N�ł�������Ǝ~�܂�B�܂莗�Ĕ�Ȃ���̂Ƃ������Ƃ��B �@�r���e���ł̓J�E���^�[�X�v�����O��1kg�`10kg�܂ŁA1kg���̃X�e�b�v��10��ނ̃X�v�����O��p�ӂ��Ă���B�J�^���O�ł̓X�v�����O���������邱�Ƃ�10kg�܂őΉ�����Ƃ��Ă��邪�A�{�[���w�b�h��75mm�ɂȂ��Ă��邽�߁A�����I�ɂ�1/2�C���`�N���X�̃J���R�[�_�[�ł����Ă����p�ɂȂ�Ƃ͌�����B�����܂ŏ��^�̃J���R�[�_�[�p�ł���B �@�ȑO���Ђ���L�������}���ŌĂꂽ���ɗp�ӂ��ꂽ�O�r���r�W����3�ŁA�L��������DVCPRO�������B�L�������͂����̂����A���悹�^�C�v�̃J���R�[�_�[�Ƀr�W����3�ł͗]��ɂ���͉߂���B�|�W�V�����ړ��̑����B�e��75mm�{�[���ł͈ړ����Ƃ̐��������ɋ�J����B����������߂�����ł��傫���p������ƃh���O�������ƃ{�[���w�b�h������Ă��܂��B����ȍ~�A���̉�Ђ̎B�e�ł͎��̉�Ђ��烔�B�W����10��100�����Q���ċ@�ޔ�Ƃ��Čv�サ�������������ɂȂ����B��͂�w�b�h�̓L�������}���̍ŏd�v�ȓ���ł���A�{�[���w�b�h�̌a���L�������T�|�[�g�̏d�v�ȃp�[�g�ł���B �@�����A���̉�Ђ̎B�e�ɌĂꂽ���Ƀr�W����3��HDV�̏��^�J���R�[�_�[�ɂ͍œK���ƌ������Ƃ�m�����BHVR-Z1J���r�W����3�ɏ悹��Ƃ܂��Ɋ����Ƃ�����B�L�������̏d�ʂ�3kg���x�ł���ΐ��������������ߕt���g���N�͂���قNj����Ȃ��Ă��ǂ��B75mm�{�[���̃t���N�V�����ŏ\�����BZ1J�����̂܂悹��̂ł����2kg�̃X�v�����O���œK�ŁA���̉�Ђ̂悤��Z1J�ɕ����p�̃t�l�i�O�r�A�^�b�`�����g�j�����t���A�Z���`�����[�̃��C�h�R���o�[�^�A�p�^�t�[�h�����t�����ꍇ��3kg�Ŋ��S�o�����X����B�܂������ȃo�����X�����̓X�v�����O�ɃX�y�[�T�[�����邱�Ƃł�萳�m�ȃo�����X�邱�Ƃ��o����B�����ăX�v�����O�������}���t���b�g#505������Ԃ������炸�A���쐫��#505�̔�ł͂Ȃ��B�������ꂩ��HDV�J���R�[�_�[�̎O�r�w�����l���Ă������������Ζ��킸�r�W����3���I�X�X������B�l�X��HDV�O�r�����O�̗l�X�ȃ��[�J�[���甭������Ă��邪�A�����[�J�[�����������������ȃr�W����3�͉��i���ȏ�̃p�t�H�[�}���X���L�������}���ɂ����炵�Ă����L�������T�|�[�g�ł���Ƃ�����B�ʐ^�͐���̌���Ŏg�p�����r�W����3��HVR-Z1J�ł���B |
2007�N06��05��(��)
|
�@�u���l�f���v�ł���B�Ȃ������������L�[���[�h�Ńq�b�g�Ă���̂��C�ɂȂ��ăA�N�Z�X���Ă݂��B �@�n�n�n�E�E�E�E�A�q�b�g���Ă����͔̂��l�ł͂Ȃ��������l�̊J�Ԃ��B��������̃y�[�W�������B���N���܂��������l�̗d�����������J�������������̂��B  |
2007�N05��21��(��)
|
�@�uDXC-537�v�������B���̃L�[���[�h��10���ȏ�̌������������B���Y���ł�����10�N�ȏ���o�����L�������Ȃ̂ɂǂ����āH�Ǝv���ă��t�[�I�[�N�V�������������Ă݂��3�䂪�o�i����Ă����B �@���D���čw�������͍̂w���҂̈ӎv�ɂ����̂ŁA�����Ƃ₩�������؍����͖����̂����ADXC-537��2006�N3�����ŃT�[�r�X��t�I���ɂȂ��Ă���B����������_���E��p���i�ɂ��C����t���I����Ă���B��p�@��DXC-537A�ɂ����Ă�2007�N3�����œ��l�ɃT�[�r�X��t���I�����Ă���B�܂�̏Ⴗ�����܂łł���B �@�I�[�N�V�����ɂ͗l�X�Ȃ��̂��o�i����A���T�C�N���̊ϓ_���炷��Α�ϑf���炵�����Ƃ����A�C���ł��Ȃ����̂ɑ��Đ����~�`���\���~�Ƃ������z���x�������Ƃɉ��l������̂��낤���H���ꂪ�N���V�b�N�J�����⍜���i�ȂǂȂ������邪�A�d�q�@��ł���r�f�I�L�������ł͂������Ȃ��̂ł��낤���B���D��ɑz��O�̌��ʂł͂����̑�^�S�~�ł���B����ǂ��납�����ɂ�����p�����������肷��d�q�@��ł̓��[�J�[�̏C���Ή��Ȃǂ��\���Ɍ������ē��D����K�v������Ǝv���B���������_�ł͍����10���ȏ�̌����͐��������f�Ƃ����邾�낤�B �@���̎ʐ^��DXC-537�����A�o�i���Ƃ͑S���W�Ȃ��B���Ô̔����Ă���C�O�T�C�g����ؗp�������̂ł���B |
2007�N05��15��(��)
|
�@�uBVW-400 �C���v�ł���B �@BVW-400�Ƃ̓x�[�^�[�J����̌^�J���R�[�_�[�̂��Ƃ����A����400���T�|�[�g�I���Ώۃ��f���ɂȂ��Ă��܂����B2006�N3�����Ɂu����_���E��p���i�ɂ��C����t�I���v�ƂȂ�A2007�N3�����Łu�T�[�r�X��t�I���v�ł���B�܂�I�[�o�[�z�[����C���̎�t���I������炵���B�K��300A��400A�͂܂����v�ł���B�ꉞ400��400A�̕��i�ɂ���ďC�����邱�Ƃ͉\�����A���Ƃ̓\�j�[�}�[�P�e�B���O�̑Ή�����ł���B �@�u���܂Ńx�[�J�����g���Ă���v�ƌ���ꂻ�������A�e���r�ԑg�����Ă��炦�Δ���悤�ɖ����ɗl�X�ȃV�[���Ńx�[�J���͊��Ă���B�������ǂ��炩�Ƃ����Βn���ǂł���B�s�S���ł̓j���[�X�Ȃǂ�HDCAM�����Ă��Ă���B�����n���ɂ����Ă�NHK����NDVCPRO HD�̗̍p�����߂��B2011�N�Ɍ����Ă�����͑S��HD�����A�x�[�^�[�J���͎p���������ɂȂ�B����\�j�[��BVW-400�̏C����t���I���������Ƃ��m����B�����������Ƀx�[�^�[�J���Ƃ����t�H�[�}�b�g���D��Ă��邩�����̗��j��������Ă���B �@VHS vs BETA�ł͂��Ƃ��Ƃ��s�ނ����\�j�[�����A���̃x�[�^�[�p�e�[�v��p�����x�[�^�[�J���͉掿�̗ǂ��ƃR���p�N�g���育��ȃT�C�Y�A�����ɂ����VHS�e�[�v���g����20���L�^����M�r�W�����Ɉ������A������NHK�̋����J���ł���M�U�i�ꉞ��NBC��ꕔ��NHK�ō̗p���ꂽ�j���x�[�^�[�J���ɂ͎��������Ȃ������B�x�[�^�[�J�������������Ȃ������̂́A20�������L�^�ł��Ȃ�M�U�ł͂Ȃ��A30�����^�ł���x�[�^�[�J��SP�𐢊E�͑I�̂ł���B�x�[�^�[�J���̃e�[�v�̓x�[�^�[�J��SP�A�f�W�^���x�[�J���A�x�[�^�[�J��SX�AIMX�A������HDCAM�܂Ōp�����ꍡ�Ɏ����Ă���B�܂�HDCAM��VTR(HDW-M2000)������ΑS�Ă̕����t�H�[�}�b�g�̃x�[�^�[�e�[�v���Đ��ł���̂ł���B�x�[�^�[�J���̓n�C�r�W�����M���Ƃ��ăA�b�v�R���o�[�g����HDCAM�̒��Ő��������邱�Ƃ��ł���Ƃ������Ƃł���B�܂�x�[�^�[�J���̏����͌݊����̏����ƌ����邾�낤�B �@�Â����̂��̂ĂȂ��ŁA���ʌ݊���ۂ��Ă����\�j�[�̃X�^�C�����f���炵���B�����炱��BVW-300A/400A�̏C����t�͓����ێ����Ă������������Ǝv���͎̂������ł͂Ȃ��͂��ł���B |
2007�N05��14��(��)
|
�@�uDV Storm �o�[�W���� ��r�v�ł���B �@DVStorm��DVStormRT�Ɏn�܂�DVStorm2�ADVStorm3�Ɛi�����Ă������B�n�[�h�E�G�A�ʂōׂ��ȕύX�͍s���Ă��邪��͂�傫�ȈႢ�̓v���O�C����h���C�o�[�̃o�[�W�����̕ύX���B�v���b�g�t�H�[����Windows2000����XP�ɕς��A�h���C�o�[�������A�b�v�f�[�g���Ă������B �@�h���C�o�[�̃A�b�v�f�[�g�ɂ���Ĉ�ԑ傫���ς�邱�Ƃ͌݊����ƈ��萫�̉��P�ł���B���݃J�m�[�v�X��WEB�Ń_�E�����[�h�ł���h���C�o�[��2.01�̃x�[�^�ł����A���̌�2.01�̃p�u���b�N�ł��o�Ă���B����������̓_�E�����[�h�ɂ����J�ł͂Ȃ��AULTRA EDIT 2 with DVStorm�Ƃ��Đ��i�Ƀp�b�P�[�W���ꂽ���̂��BULTRA EDIT 2�̃C���X�g�[��CD���g�����Ƃ�2.01.503�ɃA�b�v�f�[�g���\�ɂȂ�B 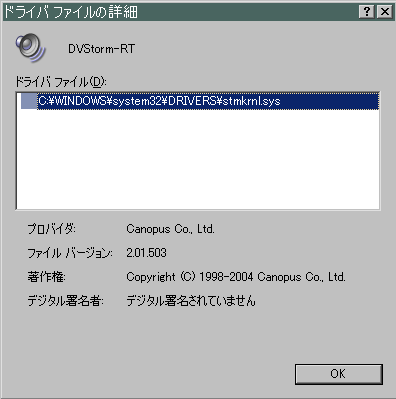 �@DVStorm�͌���HDV�Ή���VELXUS��DVStormXA�ɂ��̍������������Ɍ����邪�A�J�ł͍������p�҂������B���̉�Ђł�DVStormRT��DVStorm2������6��ғ����Ă���SD���̃m�����j�A�V�X�e���̒��j�ƂȂ��Ă���BDVStorm�����������炱���m�����j�A�Ɉڍs�o�����Ƃ����Ă��ߌ��ł͂Ȃ��B�������HD����VELXUS���g�����V�X�e����P2CAM��DVCPRO HD��Varicm�܂őΉ����Ă���B |
2007�N05��13��(��)
|
�@�u3���� ���j�A�ҏW���v�������B���̉�Ђł��߂�����g�p�p�x�̗������@�ނł���B�������d���͖���ON���A���ɐ���͉ғ����Ă���B�ʐ^�̓\�j�[��DFS-500�Ƃ���3����������ʑ��u�ŁA�����Ă̓f�W�^���X�p�C�T�[�Ƃ������̂Őe���܂ꂽ�@��ł���B���̉�Ђ�DFS-500�̓t���I�v�V�����ɉ����ăf�W�^���N���}�L�[���[��DCK-500��lj����N���}�L�[�̑��ɃJ���[�R���N�V�����ɂ��Ή����Ă���B �@�n�C���C�g�̃r�f�I���y�����K��ɂ���Ƃǂ����Ă����ԕ����Â��Ȃ�ADCK-500�̃K���}��Œ��Ԓ��������グ�A�Z�b�g�A�b�v�͋K��ǂ���ɂ���Ƃ����@�\�ɉ����A�r�f�I�L���������B�e�����f������ېF�ɕ���邱�Ƃ��o����B����܂łɉ�����ʂ̃r�f�I�𑽐��d�グ�����A�C���̐F�̓L�������̃I���W�i���ł͏o�Ȃ��B�ē��u����̋�͂����Ɛ��I�C�̓R�o���g�u���[����I�v�Ƃ����v���ɂ�����ʼn����邱�Ƃ��o�����B �@�Ƃ��낪���̊Ԃɂ��ҏW�̓m�����j�A�ֈڍs���A3�����̃G�t�F�N�g��J���[�R���N�V�������v���O�C���ŊȒP�ɍs�����Ƃ��o����悤�ɂȂ����B���ʃ��j�A�ҏW�V�X�e���͂قڕs�v�Ȃ��̂ɂȂ����ƌ����������B���ۉғ��������ł͂����������Ɍ�����B���������ꂪ��������Ȃ�s�ւȂ��Ƃ��m���ŁA�M�������̕ϊ���DVCAM����}���̃x�[�J���ҏW�ȂǁA�L���v�`���[���s�v�ȍ�Ƃ̂������ő�Ϗ�����B   �@�A�i���O����f�W�^���ֈڍs���钆�A������NHK�̋���Łu���j�t�H�[�����`���S�f�W�^������̕����R���e���c�v�Ƃ����������s���Ă����B���S�f�W�^������̖��J���������Ă���B�h�s�f�W�^�������{�i�����钆�ŕK�v�Ȕԑg�\�t�g�E�R���e���c�T�[�r�X�Ƃ͉����A�����āA������ǂ̂悤�ɒ���̂����l����B�Ƃ������e���������A�t�W�e���r�A�r�[�G�X�E�A�C�A�X�J�C�p�[�t�F�N�g�E�R�~���j�P�[�V�����Y�A���{�e���r�A�g�{���ƁA�m�g�j���������t�H�[�����͑�σA�i���O�ȓ��e�ł������B2011�N���܋߂ɔ����Ă������A�A�i���O�������ăf�W�^���������Ǝv���B �@�f��������̊����������f�W�^��������Ă������A�V���������[��������グ�Ă䂭�̂̓A�i���O���\�����X�l�Ԃ̓��]�ł��邱�Ƃ͊m���ł���B |
2007�N05��11��(��)
|
�@�u�X�e�f�B�J���I�y���[�g ����v�������B���̃L�[���[�h��4���̌���������A�������ʂɂ͂��̃u���O�ƁuHDV�����Ɩ��p�n�C�r�W�����J���R�[�_�[HVR-Z1J�v���������Ă����B���Ȃ����ăO���C�h�J���̃I�y���[�^�[�˗��̎d�����������BSEO��ɂ��WEB���ʂƂ������̂��B �@����̎d����24P�Ƃ������ƂŃL��������HVR-Z1J�ł͂Ȃ��A�i�V���i����DVX-100���w�肳��Ă���B�܂�Z1J�p�̃����[�g�R���g���[�����g�p�ł��Ȃ����ߕ��a�̃Y�[�������R������鎖�ɂ����B�����č���w�b�h�}�E���g�t�@�C���_�[�Ƃ��ă\�j�[���O���X�g�������g�p����B  �@�O���C�h�J���̃I�y���[�g�ɂ����āA�B�e�Z�p��ЂƂ��Ă͑��Ђ��g�p���Ă��Ȃ��@�ނ��g�p���邱�Ƃ����ʉ��Ƃ��Ĕ��ɏd�v�Ȃ��Ƃł͖������낤���B�������X���ŃX���[�X�V���[�^�[�t�̃O���C�h�J�����O���X�g���������Ԃ��ăI�y���[�g����Ƃ܂�Ń��{�R�b�v�ł���B���������Βʕꂩ�˂Ȃ��B�K������̏o���҂̓^�����g�ȊO�͑S�ăG�L�X�g���Ƃ������Ƃł��̐S�z�͂Ȃ������ł���B |
2007�N5��11��
| �L���� |
�R�����g(2) |
�g���b�N�o�b�N(0) |
| �����G���W���ESEO / �f������E�B�e�Z�p |
�g���b�N�o�b�NURL�Fhttp://blog.zaq.ne.jp/senri/trackback/482/
���u���O�Ǘ��҂����F����܂ŕ\������܂���
| �����G���W���ESEO / �f������E�B�e�Z�p |
�g���b�N�o�b�NURL�Fhttp://blog.zaq.ne.jp/senri/trackback/482/
���u���O�Ǘ��҂����F����܂ŕ\������܂���
2007�N05��02��(��)
|
�@�uAJ-HDC27F�v�Ƃ���������20���ȏ�L�����B�������ꂽ�y�[�W�́uPanasonic AJ-HDC27F�i�o���J���j�ɂ��720/60P�n�C�r�W�����B�e�v�ł���B���X�o���J�������K�v���Ȃ��قNjƊE�ɐZ�������L�������ł���B����20�����������L�����̂��H���ׂČ���ƃ��t�[�I�[�N�V�����ł���B http://page9.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/k45281617 ����Ȃ��̂��I�[�N�V�����ɏo�i����鎞��ɂȂ����Ƃ������Ƃ��낤���B��������������ŗ��D�����̂������̂ł���B |
2007�N04��23��(��)
�@�uXDCAM EX�v�������B�����ċt����������A�������͂Ȃ��sony.co.jp�������B�ڂ�������ƍ���������225�����̃A�N�Z�X�ł���B �@���͐�ɔ�������Ă���i�V���i����P2CAM�Ƃǂ��������邩�Ƃ����Ƃ��낾�낤�B�������MPEG2�ł͂Ȃ��o���J���Ɠ���100MBPS��DVCPRO HD�ł���B  �@���炭�͗l�q���f���A�s�̃��f�����ǂ��������̂ɂȂ��Ă��邩���y���݂ɂ������B�J�̏��ɂ���$8000���̉��i��1/2�C���`�̎B���f�q�炵���B1/2�C���`��5,8mm�̈����Ȃ�2/3�C���`��7.8mm�ɑ�������B�����p�̕W���Y�[���Ɠ�����p�ɂȂ�B����͊��҂ł��������B �@�b�͕ς�邪�T�C�o�[�V���b�g���V�@�\�荞�B�ȑO�u���O�ŏ��������A�V�����T�C�o�[�V���b�g���r�f�I�o�͂�SD����HD�ɕς�����B�A�i���O�R���|�[�l���g�o�͂�����������ƂŃt���n�C�r�W�����̐Î~������j�^�[�ɏo����悤�ɂȂ����B�A���t�@�ɏ�ʋ@������������Ɍ��������A���A���^�C���r���[�̃T�C�o�[�V���b�g���݂ł���B ��N�O�̂��̋L���ɒNjL���邪�A2008�N4���Ƀ����Y��������PMW-EX3�����\���ꂽ�B2���ɔ������ꂽ�����Y��������HDV��HVR-Z7J��HVR-S270�̎��e�[�v���f�B�A�̌��E�ɑ���PMW-EX�̓o��͂��肪�����BXDCAM EX������ǂ��L�т邩�̓��f�B�A�̉��i�ɂ������Ă��邾�낤�B �@����u���O��XDCAM EX PMW-EX3�̂��Ƃɂ��ĐG��Ă݂��B |
2007�N04��21��(�y)
|
�@�u�n�C�r�W�������p���v�Ŏ�����Ђ̃T�C�g����������Ă����B��������Ȃ��ʂ��B�������ȗ��h�Ȓ��p�Ԃ͎��̉�Ђɂ͖����B���R���̋Z�p��Ђɂ��肵�����̂ł���B �@���̎d���͑�背�R�[�h��Ђ̃p�b�P�[�WDVD�ƃI���G�A�̐��삾���A�Ȃ����̎d�������̉�Ђ��ł����̂��A���̗��R�͊ȒP���B�ߋ��̕�������̎��^���тł���B�܂�f�����^�͋@�B���s�����̂ł͂Ȃ��A�l�Ԃ��s�����̂ł���Ƃ������Ƃ��B�J�����}���ɂ���A�X�C�b�`���[�ɂ���A����܂Ōo�����Ă������Ƃ��Z�p�ƂȂ�A�\�͂ƂȂ�B �@��背�R�[�h��Ё����������Ё��痢�r�f�I�T�[�r�X�����Z�p��ЂƂ�������ɂȂ�A�ꌩ���čŌ�̓���t�]���Ă���悤�Ɍ�����B�������A���Z�p��ЂƂ����ǂ��A���ۂɃL��������U��͎̂��̉�Ђ̃L�������}���ƕς��Ȃ��B��������L�������}���̌o�����d�v�ɂȂ�B���̓��̃L�������}����M��O������܂ł�100�{�ȏ�̎ŋ����o�����A��������ȏ�̌���ŃX�C�b�`���O���Ă����̂ł���B �@���������X�^�b�t���x���Ă����̂����Z�p��Ђ̃X�^�b�t�iVE�AVTR�j�Ƃ������ƂɂȂ�B    �@�u�n�C�r�W�������p���ŏ�ʃq�b�g�����������Ŗ��V���ɒ��p�̈˗������サ�Ă����B��X�X�^�b�t�͍Ăшł̒��ɐ��s���邱�ƂɂȂ�B |
2007�N04��20��(��)
|
�@�uDSR-1�v�Ƃ̓\�j�[�̈�̌^�pDVCAM�h�b�J�u��VTR�ł���B���݃\�j�[���o���Ă���t�B�[���h�ł�HDCAM-SR���^���\�ɂ���|�[�^�u�����R�[�_�[SRW-1���c���Ă��邾���ŁA�h�b�J�u��VTR��DSR-1�͎s�ꂩ��p�������Ă��܂����B�܂�DXC-D50�ƈ�̉�����DVCAM�͖����̂ł���B�p�����������R�͊ȒP���B����Ȃ����炾�B�V�K��DSR-1���w��������z�ɐ��\���~����悹����Ί��S��̌^��DVCAM���w���o����̂ł���B�Ƃ��낪��X�Z�p��Ђ̗v�]�͏����Ⴄ�B �@�L�������Ɗ��S��̌^�ɂȂ����L�������ɂ͕����p��HDCAM�ABETACAM�ADVCAM�ȂǁA�l�X�Ȃ��̂�����BDVCAM�ł�DSR-450��DSR-400�Ȃǂ����s���f���ŁA��̌^�Ƃ��Ă̊����x�͍����B������BVP-90��BVP-70�ȂǁA����܂Ńx�[�^�[�J���̃h�b�J�u��VTR�ƈ�̉����Ă����L��������VTR���������邱�ƂŐV�����t�H�[�}�b�g�ɕύX���\���B�i���n�C�r�W�������͖����j �@���̉�Ђ̏ꍇ�ABVP-70�͍���BVV5�ƈ�̉����Ă��邪�i���Ƀx�[�^�[�J���ł̎B�e�˗�������ABVW-300��400�ƂƂ��ɍ����ғ����Ă���j    �@�����A��̌^��VTR�͉�X�Z�p��ЂɂƂ��ċ��������ł���A�t�H�[�}�b�g�̕ω��ɒǐ��ł��邱�Ƃ͌��ʂƂ��ċ@�ރR�X�g�̗}���ƂȂ�A�ڋq�ɂƂ��Ă��ǂ����ʂɌ��т��̂ł���B |
2007�N04��19��(��)
|
�@�uHDV Vision3�v�ł���B����܂�HDV��HVR-Z1J�ɂ̓}���t���b�g��#505���g�p���Ă������A�L�������}���̗v�]��Vinten��Vision3�������BHVR-Z1J�ɕ����p�̏M�iVCT-14�j���g�p�����ꍇ��3kg�̃X�v�����O�Ŋ��S�o�����X����B�������#505��3kg�ɐݒ肵�Ă���̂Ŋ��S�o�����X����̂����A�ȑOJ���[�O�̎�ނŃK���o���֍s�������i���̓��͒r���DVCAM�j�ɓ��ʂ���HVR-Z1J��Vision3�������Ă����Ă��āA���̔������r�ɖ������ꂽ�Ƃ������Ƃ��B�J�[�{���t�@�C�o�[���g���������O�r���y���ėǂ��̂����A��͂�r���e���J���[���������B�����Čy���L�������̏ꍇ�ɂ̓A���~�O�r�̕������芴������B �@���āA�̐S�̃L���������[�N�����A����/����/�߂̃p���͂������Ƀr���e���ł���B����ŏ�肭�U��Ȃ���ΐl���̏I��肾�B�����ăX���[�p���̂��߂Ƀh���O�����߂ɐݒ肵�Ă��o�b�N���b�V�����������R�Ɏ~�܂�B��������o�����X���[�Y���B  |
2007�N04��18��(��)
�@�uP2CAM�v�Ƃ����L�[���[�h�BP2CAM�Ƃ͏����̔����̃������[�ɂ��J���R�[�_�[�ł���B��ɏ�����AG-HPX555���������B �@����HPX555�����\����Ă���NAB2007�̃\�j�[�u�[�X�ňٕς��N�����Ă���炵���B�������NAB2007�֎��@�ɂ����Ă���Z�p��Ђ�H������͂��j���[�X�ł͏�����P2CAM�ɑR���锼���̃������[�J���R�[�_�[�Ƃ��ăt���b�V�����������̗p����XDCAM EX�����\���ꂽ�炵���B����̎ʐ^�������Ō��邱�Ƃ��ł����B �@HDCAM�ɂ���Đ��E�����[�h����NHK�n���ǂ�DVCPRO-HD�̗p�ɂ���Ēn���I�ɔs��͂������APCAM�ɂ���Ĉ����Ă��������ɑ��ă\�j�[�͐V�����킢�ݎn�߂��BHDV�ɎQ�������A�Ǝ���P2CAM�H���Ői��ł��������w�c��XDCAM_EX�ŃT���f�B�X�N�̃������[���̗p�����\�j�[�BHD/SD���݂ō��ׂƂ���f���ƊE�Ń��[�U�[�͂ǂ����I�Ԃ̂��A�����ւ��[���킢����������B �@���āA���̉�Ђ͂ǂ�����I�Ԃ̂��H �@�����͂Q�ł���B�Z�p��ЂƂ��Ă͑o���ɑΉ����Ȃ���Ȃ�Ȃ����낤�B�����ݎ��̉�Ђ��Ή����Ă���t�H�[�}�b�g�̓�CAM/DVCAM/DVCPRO-25/50/HD�A������HDV�AP2CAM�AHDCAM�����A�܂��V���ȑΉ��𔗂��邱�ƂɂȂ�B�t�H�[�}�b�g�����ɐU����͍̂ŏI�̎����҂����邱�ƂȂ���A�Z�p��Ђ��U���đ����Ă���̂��B �@���Ȃ݂�XDCAM EX�Ƌ�������P2CAM�J���R�[�_�[�͉��̎ʐ^AG-HVX200�ł���B   �@NAB2007�̌��n���|�[�g���V�X�e���t�@�C�u����̃|�[�^���T�C�g�Ō��J����Ă���B���Ă��邾���Ń��N���N����B�������ڂ̓łł�����B |
2007�N04��12��(��)
|
�@�uWMV���c�u�c�ɕϊ��v�ł���B���̃L�[���[�h���ǂ���������B��Ƃ͌����ē�����̂ł͂Ȃ��B�t���[�E�G�A��WMV����VIDEO_TS�������o����DVD���Ă��������B�������d���Ƃ��Đ����������Ƃ͏o���Ȃ��B���������₢���킹������t���[�E�G�A�̃_�E�����[�h�T�C�g��m�点�Ď����ł���Ă��炤�悤�ɂ��Ă���B �@���������PC��GYAO�̓��敔����������DVD�ɏĂ����肵�Ă���B����͂����܂Ōl�I�Ɋy���ނ��߂̍�ƂƂ�����B�d�g����^�悷��ꍇ�̓G�A�`�F�b�N�Ƃ��������A�l�b�g����^�悷���Ƃ͂Ȃ�ƌ����Ηǂ��̂��낤���BIP�`�F�b�N�A���邢��IT�`�F�b�N�Ƃł������̂��낤���H������ɂ��Ă��d���ł��Εs�@�s�ׂƂȂ�B �@�����͎����HDCAM���P�ł���B�T�u�͂�͂�HDV��HVR-Z1J���B�V����ǂ������ŁA�����オ�肪���҂ł��������B��X�̎d���̓G�A�`�F�b�N�ł͂Ȃ��A�G�A�`�F�b�N�����f������邱�Ƃł���B |
2007�N04��11��(��)
|
�@�u���^�[���X�C�b�`�Ƃ��v�������B���X���̃L�[���[�h�����O�ɏo������B�������ꂽ�y�[�W�̃g�b�v�����^�[���X�C�b�`�̍������Љ�����Ă����L�������}������̃y�[�W���������̂ŁA��肽���l�ɂ͂����̂ł͂Ȃ����낤���B �@�f�ڂ��Ă���ʐ^�̓\�j�[�̃��^�[���X�C�b�`CAC-6�ł���B���^�[��1��2�̑��ɃC���J���̃}�C�N�X�C�b�`���t���Ă���B�C���J���ɂ̓P�[�u���̒��Ԃ�w�b�h�Z�b�g�ɃX�C�b�`���t���Ă��āA���i�͉��̉�肱�݂�h�����߂�OFF�ɂ��Ă��邪�A�K�v�ɉ����ăL��������������b���Ȃ���Ȃ�Ȃ��ꍇ������B����������Ń����Y�𑀍삵�A�E��Ńp���_�������Ă���ꍇ�̓P�[�u���ɕt����ꂽ�g�O���X�C�b�`��G�邱�Ƃ��o���Ȃ��B���������ꍇ�ɂ�CAC-6�̃}�C�N�X�C�b�`�������Ȃ���b�����ɂȂ�B���������[�J�[���̃��^�[���X�C�b�`�͂������ɍ����ŁACAC-6�͐ŕ�95,000�~������B��͂胊�^�[���X�C�b�`�͎��삪�ǂ������ł���B |
| �O�� | ���� |
�@
PHOTOHITO�u���O�p�[�c
|
�j�b�N�l�[���FSENRI �s���{���F���E���{ �f������/�B�e�Z�p��� (���j�痢�r�f�I�T�[�r�X ��\������� �k�����x�����q���b�eHP�̊Ǘ��l�ł��B��낵�����肢���܂��B ���F�X�o�܂��� »���킵������ �o�C�I�O���t�B�[ |


















