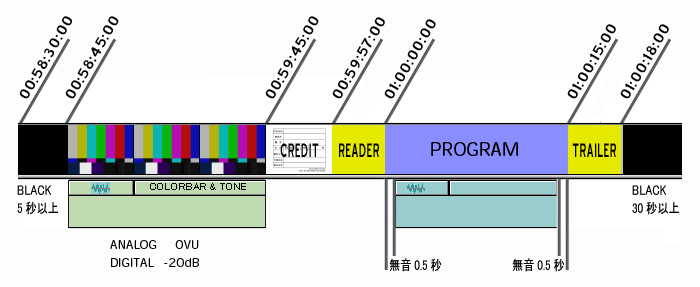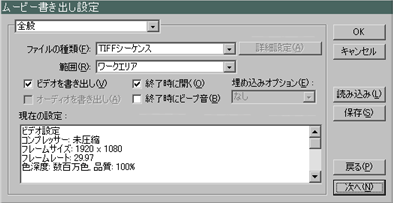2007年01月17日(水)
|
「ステディーカム 自作 簡単」での検索があった。ヒットしていたのはこのブログのカテゴリー1であるVIDEOだった。「ステディーカム 自作 簡単」というキーワードを見るためにグーグルのキャッシュを参照したところ3つほどの記事がハイライトされていた。特に沢山ハイライトされていたのは1/3の「HDV移動撮影システム」だった。 ステディーカムの様なスタビライザーを自作されている方はかなり居るようで、色々なサイトがヒットする。しかし自作は決して簡単ではなく、それなりの費用と時間を費やさねばならないようである。私の会社でも自前のスタビライザーを導入しようと何種類かのスタビライザーをテストしてみた。その結果最も望んでいる性能を持っていたものがグライドカム4000Proとスムースシューターの組み合わせであった。1時間程度のテスト撮影を行った結果、「これはいける」という手ごたえを感じ、早速本格的なテストを監督とともに行った。 テストはキャストを入れたリハーサルで5時間に及んだが、監督いわく、「いいよ!ハンディーとはぜんぜん違うね!これでいこうよ」と言う結果になった。そして「HDVスタビライズショット」で売っていけるよ!という監督に煽てられて、購入することに決まった。 以前ステディカムSKにベーターカムを搭載して撮影したときは30分あまりでまいってしまったが、グライドカム4000ProとスムースシューターにHDVのHVR-Z1Jの組み合わせは大変楽だった。午前3時間、午後2時間のリハーサル中、50を過ぎた私でも容易に担ぎ続けることが出来たのである。今後は「HDVキャメラを使ったお手軽特機撮影」の一環としてより一層充実を図りたい。現在「手軽な予算でステディーショットを実現するグライドカム 4000 Pro+スムースシューターの紹介」として暫定版のWEBページを公開しているが、撮影サンプルの動画配信などを加えたページを企画している。HDVやメモリーカード、ハードディスクを用いた小型ハイビジョンキャメラはまたもや我々に多くの可能性を見出させてくれる。 |
2007年01月16日(火)
|
「ポータブレイス ロケ」だ。以前にもこの様なキーワードが有ったと思うが、ポータブレイスは我々にとって必需品である。写真はモニターのケースだが、他にも様々なものが作られている。会社でもモニターケースの他にキャメラのレインカバーなどもポータブレイス製のものを使っている。おそらくこれが最も使いやすく、丈夫なためだろう。つまりポータブレイスはVロケの必需品である。 ところが最近私が気になっているケースがある。 Working Easyという会社の製品だ。イタリアの会社だが輸入しているのは大阪の摂津金属である。実は私はかれこれ40年ほど前からこの会社の製造する電子機器用のシャーシやケースを購入している。子供の頃から機械や電気工作が好きで、無線機や音響機器を数々自作してきた。そのときに使っていたものがIDEALブランドのものだった。また映像に携わるようになってからも19インチラックなどは摂津金属の製品だ。 この馴染み深い会社が扱う様々な製品の中に「プロ放送機材用ソフトバッグ」が有った。実物はまだ見ていないが、写真で見る限りはなかなか良さそうだ。現在会社で使っている三脚ケースがビンテンを除く5本分がそろそろ経たってきたため、新しいものを揃えようと考えていた。色合いがビンテンに似ていてデザインも良い。暇になれば八尾まで出向いて実物を見た上で購入を考えてみたい。子供時代から馴染のある会社の製品を使えると思うと嬉しくなる。 |
2007年01月15日(月)
|
「業務用 レンズ ズームコントロール」という検索だった。ヒットしていたページではマンフロットのズームコントロールを紹介しているが、実際に使うことはまず無いといえる。というのも、大阪ではズームに電気を使うことは恥ずかしいという風潮が残っているからだ。つまりズーミングはキャメラマンの腕の見せ所であり、一種の職人芸だからである。しかし私はキャメラマンに絶対手動ズームを要求するわけではない。ズーミングしながらのフォーカスフォローはけっこう大変なことで、右手でズーム、左手でフォーカス(箱レンズを装着したスタジオキャメラは逆で、押し引きレンズでは右手に操作が集中している)を操作できる電動ズームはシーンによっては重要な機能である。そしてNHKでは電動ズームが標準スタイルで、手動ズームはイレギュラーだそうだ。また、最近の放送用レンズは電動ズームの速度がシーソー式のサーボとは別に高速から低速まで自由に選べるようになっている。さらにズーミングの終端を電気的に設定でき、指定したサイズで自動的に止まってくれる。とても便利になっている。しかし実際にそれを現場で使っているキャメラマンは知らないし、私の周りでそれを使っているのを一度も見たことが無い。つまりレンズのコストを上げるだけの機能ということになっているようだ。 それよりもズームリングのシリコーングリスの粘性調整や、定期的なメンテナンスを心がける方が私にとっては重要なことである。レンズのメンテナンスを怠らなければ手動ズームでも滑らかな動きが出来るし、手動ならではの加速、減速に気持ちを込めることが出来る。そして監督が超スローズームを要求する場合は電気ではなく、オイルダンプ式のズームレバーも有る。「業務用 レンズ ズームコントロール」に対する回答はこれしかないだろう。思うタイミングでスタートし、ベストな速度でズーミングする。そして気持ちよく減速した後、指定のサイズで滑らかに止まる。フォーカスフォローが必要な場合フォーカスフォローを取り付けてセカンドが操作すれば良い。 と思うのだが、ビデオではセカンドやサードが付くようなことは無く、フォーカスもキャメラマンの仕事である。ではどうすれば良いか?・・・それが電動のズームコントローラーだ。今ではレンズメーカーだけではなく、様々なサードパーティー製のものが販売されている。自分のスタイルや予算に合わせて選ぶことが出来る。 下手なズーミングをされるよりも、電気を使っても美しいズーミングをしてくれるキャメラマンの方が良いに決まっている。これが「キャメラマンに絶対手動ズームを要求するわけではない」理由である。だが実際に電気を使うキャメラマンは私の周りでは皆無である。いい職人さん達に恵まれているといえるだろう。 |
2007年01月11日(木)
|
「映像制作 番組交換基準 タイムコード」だった。 おそらくCMか何かのタイムコードの基準を探されていたのだろう。番組交換基準の複雑な部分は知らないが、映像制作をしていて最初に苦労することは納品時の約束事である。不良素材にならないための信号の基準値などは雑誌やネットで簡単に手に入る時代になったし、今日のようにデジタル化された時代では機械任せでも十分通用するようだ。ところがタイムコードに関しては放送関係はドロップフレームが使用され、VPなどではノンドロップフレームが普通になっている。そしてタイムコードのスタートも01:00:00:00を本編スタートとする場合と、日テレやNHKのように10:00:00:00開始というものもある。東京でNHKの音効をやっている古い友人のI氏は10:00:00:00開始の方がトータルデュレーションがすぐに判るから便利だよ」といっていたが、01:00:00:00に慣れると10:00:00:00で始まるタイムコードは気持ち悪い。ついでに言えば、なぜ00:00:00:00ではなく01:00:00:00かといえば、昔の編集機がマイナス側、つまり23時のタイムコードを計算できなかったからだそうだ。ただしこれは人から聞いたもので調べたわけではない。 ネットでタイムコードのフォーマットを検索してみたが見当たらなかったので、「CM納品 タイムコード」などを検索された場合に役立つように私が持っているフォーマットを画像でアップしておく。クリックすると大きなサイズで表示される。 |
2007年01月10日(水)
|
「連番静止画出力」でのアクセスだ。ヒットしていたページはテレシネ紹介のフィルム&フィルムズだった。連番静止画には様々なものがある。例えば3Dアプリケーションでコマごとの静止画を出力する場合や、動画から各コマごとの静止画を書き出す場合などだ。用途も様々で合成用の背景であったり、学術用途の解析用であったりする。 私の会社の場合はどちらかといえば後者の学術用途が多いが、アニメーションのクリエーターから送られてきたアニメの連番静止画をビデオやDVDに出力したりすもする。バラバラの元絵を連番でタイムラインに並べて動かす瞬間は何度やっても感動する。いずれの場合もこれらの作業はコンピューターのお世話になる。静止画の形式も様々なものがあり、BMPやTIFF、TARGAなどだ。そして出力形式も1/5圧縮のDV形式から非圧縮のAVIファイルなど諸々だ。これら全てコンピューターがあっての仕事である。電子計算機に感謝! |
2007年01月06日(土)
|
「ブラウン管式のモニター」だった。 液晶全盛だが、やはりSDはブラウン管の方がきれいだ。画素がなく、信号通りの走査線を描いてくれるからだろうか。ハイビジョンでは液晶がきれいなのだが、まだまだSDがなくならない。上の写真はSONYのBVM-9045QDでノンリニア編集のオペレーター用モニターに使用している。また、14インチはPanasonicのTM-1410BTaを4:3/16:9のスイッチャブルに改造して使用している。 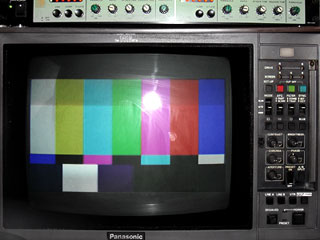 |
2007年01月03日(水)
|
「HDV移動撮影システム」という検索だ。私の会社では一昨年から「HDVキャメラを使ったお手軽特機撮影」を推し進めている。これまで予算の都合で導入しにくかったレールやクレーン、ステディーカムなどをキャメラのコストが下がった分を特機に廻すことで実現しようというものだ。 昨年末に東京の制作会社から話があり、今回はステディーカムを使いたいということだった。もちろん大きなキャメラにステディーカムSKやEFPを使用すれば非常にきれいな移動撮影が出来る。しかし機材やオペレーターのコストを考えると予算オーバーである。ところが監督から「HDVを使ってみたい」との希望があり、話はとんとん拍子で進んだ。従来の予算枠でステディーが使えるのは良いが、オペレーターまでは予算がない。ということはキャメラマンがステディーカムのオペレーターを兼務しなければならない。かなり昔だが、私自身がベーターカムをステディーカムに乗せて撮影したことがある。一応必要なカットは撮ったが、体は大変だ。普段使わない筋肉を使ったため、数日間は筋肉痛に苦しんだ。 そこで登場するのがabcプロダクトのHandyManSet-SとEasyFlexだ。HDVクラスのキャメラに合わせて作られたもので、総重量はステディーカムSKの1/5程度だ。これなら筋肉痛に苦しまずにオペレートできそうだ。年末に無理を言って機材屋さんからお借りしてきた。正月休みの間にテストとトレーニングである。1/13にロケハンとキャメラテストを行うが、それまでには実用レベルに追い込めそうである。 そして別なプロダクションからも同じくHDV移動撮影の依頼があった。こちらの方はレールを使った撮影だが、従来のレールのようなスタイルでは不可能な内容である。これについては現在私の頭の中にあるイメージを具体的なものにしなければならない。アイデアは画期的なものだが、精度などで解決しなければならない問題がある。特機開発部?の想像力にかかっている。 下の写真はabcプロダクトのHandyManSet-S+EasyFlexだ。 |
2006年12月23日(土)
|
「コーワ スイッチャー」である。コーワとは、「コルゲンコーワ」や「キャベジンコーワ」などの医薬品で有名だが、映像機器の製造・販売も行っている。最も有名なものはテロップ装置のオペークキャメラや時報テロップだ。しかし光学製品でもスポッティングスコープやコーワシックスという6×6のレンズシャッター式ブーニーカメラが有名だ。医薬品のイメージが強いが、業界では光学機器や放送機器でも確かな製品を出している。検索キーワードのスイッチャーとしてはマトリクススイッチャーなどがあるようだ。 私の会社でも設立当初はテロップカード(テロップ用の白抜きの版下)を使ってポスプロでのスーパー入れをよく行ったが、マックにNTSCビデオカードを導入してからは自社内でテロップを作るようになり、テロップカードは過去のものとなってしまった。 |
2006年12月21日(木)
|
再び「Vision10」である。今度はこのブログがトップで挙がっている。先日も書いたので改めて書くことも無いと思うが、面白い事に気付いた。 Vision10と書いて何と読むかである。当然ビジョンテンである。ところがVision100や11、20はというと突然和洋折衷になる。下の写真はVision100だが、これはビジョンひゃく(100)となる。  サクラーの場合もビンテンと同様にVIDEO14やVIDEO18、VIDEO20など和洋折衷が一般的だ。おそらく100や11は英語よりも日本語の方が言い易いからだろう。性能や見た目には影響ないことだが、Vision10というキーワードを見てふとこんなことを考えてしまった。 明日(また今日になってしまったが・・・)の自転車博物館の撮影ではHDVを使用するため、三脚はビンテンではなくマンフロットを使用する。キャメラの大きさによってはビンテンが最高ということにはならない。 |
2006年12月18日(月)
「テロップリアルタイム出力」という検索だった。検索結果には随分と古いページが上がっていた。「テロップリアルタイム出力」ということから、編集システムではなく、送出システムのことだろうか。放送や送出では一般にシステムの最終部分でDSK(ダウウストリームキーヤー)によってテロップを挿入する。単独のDSKもあれば、スイッチャーの中にDSKを備えていたりする。そしてテロップの信号源としてテロップ専用の装置(コーワが出していたテロップカード専用のシステム)やコンピューターを使ったCG(コンピュータグラフィックスではなく、キャラクタージェネレーター)などを使用する。(CGには野球などのスポーツ専用の送出システムなどもある。)最近では朋栄のVWSシリーズなどがあり、リアルタイムに3Dエフェクト付きのテロップ送出が可能である。 上の現場写真ではマックにNTSCボードを追加してリアルタイムにテロップ、スーパーを出せるように構築している。このシステムは外部同期に対応していて、ジェンロックを掛けることでフレームシンクロナイザーを内蔵しないスイッチャーでも同期結合が可能だ。そしてPhotoshopのレイヤーから透明部分をアルファチャンネルとしてキー信号を発生できるようになっている。アルファチャンネルをキー信号として使用することでフィル画面に黒があっても黒く抜くことが可能になり、フルカラーのスーパーを出すことが出来る。  写真は古いパワーマックにG3カードを追加して使用しているが、現在は青白ポリタンクを使っている。このNTSCカードはG4との相性が悪く、G3での使用が条件となる。システムもOS-9が安全だ。このカードがあるために今尚マックを手放せないといった方が良さそうだ。テロップを現場でリアルタイム出力するにはCGも重要だが、キー信号と外部キー入力を備えたスイッチャーが必須になる。 |
2006年12月16日(土)
|
「ビデオ信号静止画取り込み」という検索である。検索結果はかなり古いページで、マックを使ったビデオボードの比較ページだ。当時はこういった作業のために数十万のビデオボードやアクセラレーターを使用していたが、今では数万円のボードでも十分に実用的な静止画をキャプチャーすることが出来るようになった。もちろん業務用のビデオ編集ソフトから静止画を出力するのが最も良いが、例えばDVDビデオから静止画を取り出す場合に限定すれば、PCやDVDドライブのバンドルソフトやオマケソフトで十分である。もちろん追加のビデオボードなどのハードウエアも必要なく、PCのみで作業できる。 先日小田純平さんの記事が産経新聞に掲載された。その時に使用した写真はDVDからキャプチャーして、制作会社にメールで送ったものである。静止画の取り出しに使用したソフトウエアはインタービデオのWinDVD4だった。これはDVDドライブに付属していたバンドル版で↓これがその写真だ。  今日16日はエキスポランドでコスプレイベントの撮影がある。オフィシャルサイト用の写真だが、メインカメラマンは会社の若手に任せている。私は宮内タカユキ氏のライブやかわいいコスプレイヤーを楽しみながら撮影しよう。私のデジカメは当然一眼レフではなく、Cyber-shot R-1とT-9だ。 |
2006年12月15日(金)
|
「カメラ リターンスイッチ ケーブル」というキーワードだ。以前にも同じようなキーワードでの検索があった。 スイッチャーによるEFP収録ではリターンが無ければ不可能だ。写真は私の会社で使用しているリターンスイッチだ。レンズ側のコネクターとスイッチを日本橋で購入して自作している。 よく似たものにレックトリガーがある。  同じコネクターに差し込んで使用するが、スイッチの種類が異なる。リターンスイッチは無音だが、トリガー用はカチカチと音がする。このスイッチはレックスタート時にキャメラが揺れないために使用する。同ポジ撮影では必須の道具となる。リターンスイッチはマルチキャメラ収録に使用するものだが、トリガーはENGスタイルで使用する。 二つのスイッチの共通点はレンズ側のコネクターと連結するリングネジを外していることだ。撮影時には敏速な抜き差しが必要なため、ネジで締め付けて固定するとかえって不便だ。コネクターのフリクションで十分である。 |
2006年12月14日(木)
|
「BVP-T70」での検索だった。BVP-T70とはBVP-70のCCDブロックをキャメラヘッドから分離できるようしたもので、キャメラヘッドと一体化した場合はBVP-70と同様に使用できる。その分割高だが時にT70で無ければ撮影できないものもある。例えば狭い室内での撮影でキャメラの引き場所が確保できないときなどだ。 写真はロイヤルホストのCMを撮影した時のものだが、狭い調理場では非常に有効だった。また、車載キャメラや狭い社車内の撮影でも活躍する。 BVP-70はCCDがFITだが、IT型を使用した低価格のBVP-T7なども販売されていたが、それでも数百万もする高価なキャメラだ。ところが最近ではナショナルのDVX100AやHVX200、そしてソニーのZ1J、V1Jなど、MiniDVテープを使用する高画質で低価格な小型キャメラが出現し、T70を使わなくても同等のものが、それも必要に応じてハイビジョンで撮影できるようになった。 今度またインテルのVPを撮影することが決まり、従来はイケガミのHL-DV7Wを使って撮影したものが、今度はHVR-Z1JとV1Jをステディーカムで使用する。キャメラの進化は凄いものだ。 |
2006年12月13日(水)
|
「Vision10」という検索だった。 Vision10はイギリスの三脚メーカーのビンテンが作る三脚で、放送関係では最も多く使われているのではないだろうか。Vision10は発売後かなりの年月を経てきたもので、発売当初はサクラーと激しく競合したが、現在ではサクラーの黒いヘッドよりもビンテンのベージュのヘッドの方が多い。Vision10はひとまわり大きいVision100へと進化し、Vision10に変わるものとしてVision11が発売されている。私の会社でもVision10、Vision11を使用するが、私はVision10の方が好きだ。メンテナンスも定期的に実施し、これまでに2度オーバーホールも行っている。性能的にはVision11の方が優れているのだが、道具の評価は使い手の好みに大きく左右される。もしVision10とVision11のいずれかを差し上げると言われれば私は迷わずVision10を選ぶ。非常に完成度の高いキャメラサポートだ。 Vision10といえば代理店との間でこんな話があった。実は三脚ケースのファスナーが壊れて破れてしまった時の事だ。修理できる状態ではなかったため、新たに購入するか、代用品を手に入れる必要があった。もちろんオリジナル品がベストだが、価格が8万もする。当然値引き交渉をするわけだが、その中で私が「あの青いケースはキャメラマンの誇りだ。サクラーの黒いケースなんて・・・」と言ったことがどうやらビンテンに伝わったようだ。10日程経って会社に真新しい純正ケースが届いた。だがそこには請求書は付いていなかった。「進呈」である。商売の機微というものだろうか。キャメラマンの誇りを感じてくれたビンテンに感謝した。そしてそれまで100%ビンテン派だった私はこの時を境に200%ビンテン派になった。 |
2006年12月07日(木)
|
「HD 流用 SD 20倍」である。これはレンズのことだ。ハイビジョン用のレンズをスタンダードの解像度、つまり地上波アナログに使用すること、もしくはその逆で、SD用の20倍をHDに流用ということになる。 ハイビジョン放送がMUSEでスタートした頃のキャメラは1吋撮像管が使用され、そのままではSDに流用は出来なかった。しかしキャメラが高性能化し、今はSDと同じ2/3インチCCDが使用されている。また、レンズマウント、フランジバックとも同じ規格になっているため、HDレンズはSDに流用可能だ。可能というよりも、蛍石をふんだんに使用したSDレンズよりもはるかに高性能で、オーバースペックということになる。しかも使用上は問題ないどころか、より高性能になる。ただしHDレンズはSDレンズに比べると大きく重くなる。 ・・・・・と思っていたのだが、様子は随分と違ってきた。 上の写真はフジノンの21倍HDレンズのHA-21×7.8だが前球が82φでSDの14倍〜16倍と変わらない。逆に100φの20倍〜22倍よりも小型軽量になっている。性能は勿論HDだ。下の写真は明日の現場のためにIkegami HC-D45に取り付けたものだが、その大きさはSDの15倍と変わらない。  明日はMキャメラマンがヴィッセル神戸の取材にこのレンズとキャメラを持って行く。SD用のJ20a×8よりも高性能で小型であれば誰もが使いたくなるのは当然だ。私は明日仕込み、明後日本番の2CAM/EFPの現場へ出向く。悲しいかな旧型のJ14a×8.5とJ15a×8になる。 ちなみにSD用のレンズもHDキャメラに取り付けることは可能だが、SDレンズではHDの解像度には及ばない。絶対に止めた方が良い。SD用でHDに使用可能なレンズは単焦点のシネレンズか、旧型のJ14×8くらいだ。  |
| 前へ | 次へ |
PHOTOHITOブログパーツ
|
ニックネーム:SENRI 都道府県:関西・大阪府 映像制作/撮影技術会社 (株)千里ビデオサービス 代表取締役& 北八ヶ岳麦草ヒュッテHPの管理人です。よろしくお願いします。 ↓色々出ます↓ »くわしく見る バイオグラフィー |