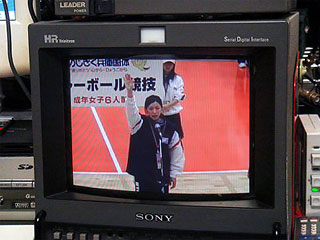2006�N10��08��(��)
 �@�uDF/NDF�v�Ƃ����������BDF�Ƃ̓h���b�v�t���[���ANDF�Ƃ̓m���h���b�v�t���[���̗��̂ł���B �@�uDF/NDF�v�Ƃ����������BDF�Ƃ̓h���b�v�t���[���ANDF�Ƃ̓m���h���b�v�t���[���̗��̂ł���B�@�e���r�����������ł���������ɂ͑��݂��Ȃ��������t���B����̓J���[�����ɂȂ��Ă���K�v�ɂȂ������̂ł���B �����ƃJ���[�̈Ⴂ������� 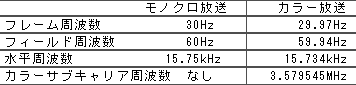 �ƂȂ�A1�b�Ԃ�����̃t���[������0.03���Ȃ��Ȃ��Ă���̂��킩��B �@�e���r�����̃J���[���������Ă��P�b��30�t���[���ő��邱�Ƃ͖��Ȃ������̂����A�����̔����e���r���ł��Ȃ����߁A�����d�g�Ŕ����ƃJ���[��������悤�ɁA�J���[�����������T�u�L�����A�Ƃ��Č�t�����B���̌��ʏ��ʂ������A���ԓ��Ƀt���[���𑗂肫��Ȃ��̂ł���B���̂��߂Ɍv�Z��29.97�ɂȂ��Ă��܂����̂��B�����J���[�łP�b��30�t���[���ő����1���Ԃɂ���3.6�b�̂��ꂪ������B���̌덷���C�����邽�߂ɁA�w�肵���t���[�����^�C���R�[�h�������I�ɔ����K�i���h���b�v�t���[���ł���B���m�ɂ�29.97�t���[����1�b�Ԃ����A�m���h���b�v�t���[���ł́A30�t���[����1�b�Ƃ��邽�߁A�^�C���R�[�h�̕\���́A�����Ԃ��������Ȃ�B�h���b�v�t���[���͎����Ԃƍ��킹�邽�߂�0, 10, 20, 30, 40, 50�����������F���F�b�F00�̊J�n�ʒu�łQ�̃t���[���ԍ��i0,1)���J�E���g����������߁At�b�F29�t���[���̎���t+1�b�F02�t���[���ɂȂ�B �@�܂��A������������₱�����b�͈�ʂ̐l�͋C�ɂ��Ȃ��ėǂ����Ƃ����A��̗��R�Ńr�f�I�̃^�C���R�[�h�������ԂɈ�v�����邽�߁A�ǂɔ[�i����ꍇ�̓^�C���R�[�h���m���h���b�v�t���[���ɂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�����m���h���b�v��30���̊��p�P�����ƍŌ��1.8�b���������Ԃ���͂ݏo���Ă��܂����ƂɂȂ�B���̂��߂ɔԑg������ł̓h���b�v�t���[�������ɂȂ��Ă���̂ł���B������15�bCM�ł�DF�ł�NDF�ł����͖����B15�b�ł̌덷��0.45�t���[�����������Ȃ��̂ł���B �ʔ����b���������B �A�}�`���A����u�v���p�̓m���h���b�v�t���[�����I�ׂĂ����ł��ˁv ���u�H�H�H�v �A�}�`���A����u���̃R���s���[�^�[��DV��ҏW����ƃR�}�������č���܂��B�v ���u�I�I�I�v �ƒ�Ŏg�p����miniDV�̓^�C���R�[�h�������ԂɈ�v����悤�Ƀh���b�v�t���[�����g�p����Ă���B�����R�}�����͕ʂ��B�����炭PC��n�[�h�f�B�X�N�̃X�y�b�N���Ⴂ���߂ɃR�}�������N�����̂��BNDF�ł�����͓��l�ł���B �@���č������l�N�͂̂��������́A�s�N�͍�������k�̒�������܂�̎�ނɍs���Ă���B�j���[�X�ł����m���Ǝv��������Ŏ������������B���܂���ނ��Ă����c�Ƃ͈�������A�C��t���Ă��炢�����B���͂Ƃ����ƁA�X���̓{���̎B�e�A�ҏW�A��ꐶ����VP�Ȃǂ̓O��n������E�o���A�����́u��������}���f�[�v�����邱�Ƃ��o�����B������33�{�����Y���g�p����2CAM���p���B�悤�₭�{������̏o���������Ă����悤���B |
2006�N10��05��(��)
|
�@�u�W���s�^�[�z�[���@�f�������v�������B�W���s�^�[�z�[���͈ȑO�u�a�c�R��������فv�Ƃ����AURL��http://www.town.wadayama.hyogo.jp/jupiter/�ŕ��Ɍ������S�a�c�R���ł��������̂��A���쒬�E�a�c�R���E�R�����E���������������Č��݂͒����s�a�c�R���ɂȂ��Ă���BURL��http://www.city.asago.hyogo.jp/jupiter/�Ƃ����킯���B �@�W���s�^�[�z�[���Ŏd�������Ėʔ��������̂́A���Ɂu�X�^�b�t�N���u�v�Ƃ����g�D������A�W���s�^�[�z�[���̕���^�c����`���Ă��邱�Ƃ��B�����B�e�ɍs�����Ƃ����吨�́u�X�^�b�t�N���u�v�̐l����`���āH����āA�d�C�X�H�̐l�����̃����o�[�ɐF�X�Ɖ�����Ă����B �@����Ȓ����֍�������L��������M�N�����̒��p�̋Z�p�w���ōs���Ă���B����܂ő������o���[�{�[���𒆌p���Ă������A6������̓n���h�{�[���ɂȂ�B�ނ��烁�[�����͂��Ă����̂ŏЉ�悤�B �@�@ 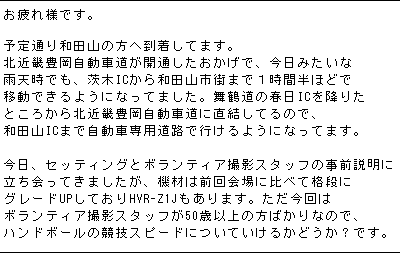 �@�a�c�R�ɍs��������ϕ֗��ɂȂ����B��V�艷���ւ������ɏo��������B�������}���ꍇ���A�n��`�����p�ł���B�ɒO����A�n�܂�40���ōs����B�����͕Г�11,000�~��1��2�������Ă���B�܂��A�A�n�n��̏Z����Ζ��҂ɂ͎����̂�����^���������x������B �ڂ������A�n�����}�̃T�C�g�������������������B |
2006�N10��04��(��)
|
�@�uHDV�B�e�v�ł���B�ȑO�Ȃ�x�[�J���w�肾�����B�e��DVCAM��DVCPRO�ɂȂ�AUNIHI��HDCAM�ADVCPRO HD�ɕω����Ă����B�����č��傫���ς�낤�Ƃ��Ă�����̂�HDV�ł���B �@HDV�t�H�[�}�b�g�̃L��������1080i��HD�M����MPEG���k����DV�e�[�v�ɋL�^���邪�A480i��SD�M���̏ꍇ��1080i��HD�M�����_�E���R���o�[�g����SD�L�^���Ă���B���̂��߃n�C�r�W�����Ɍ��炸SD�ɂ����Ă�CCD�i����CMOS�j�̉�f��S�ėL���ɏo����B���̂���DVCAM���[�h��16�F9���C�h�̏ꍇ��52��f�N���X�̕����p19�F9�L�������Ɍ���肵�Ȃ��f�����L�^�ł���B����ׂ�HDV�ł���B �@���̉�Ђł�����܂ŕ����p�x�[�J���w�肾�������̂����X��HDV�ł̔����ɕς���Ă����B����͎B�e��̒ቿ�i���ɂȂ�A����グ�ቺ���������ƂɂȂ�B��������͋@�ޔ�����Ȃ����̂ł��邩�瓖�R�ŁA�N���C�A���g�ɂƂ��Ă͔��ɗǂ����Ƃł���B �@���������̂܂܂ł͋Z�p��Ђ͂���Ă䂯�Ȃ��B�V���Ȑ헪���K�v�ɂȂ�B�����Ŏ��̉�Ђł͏]���̐���R�X�g���ێ����邽�߂ɓ��@���g�p���邱�Ƃ�E�߂Ă���B�N���[����[���A�����ċ�B�Ȃǂ��B�܂������^HDV�L���������g�p�����I���{�[�h�L�������ł���B�����̂��Ƃ��]����2/3�D�����L�������ōs���Ă����̂ł�HDCAM��V�l�A���^�Ɠ��l�̎B�e�R�X�g�ƂȂ�A�N���C�A���g�ɂƂ��ĕ��S���ɂȂ�B�����HDV�ōs���Ƃ���ɈӖ�������Ƃ����邾�낤�B���ɃW�u�i�~�j�N���[���j���g�p�����B�e�ł̓L�������̎��ʂ������������Ƃŕ����p�L�����������ǂ����ʂ��o�Ă���B�܂��~�j�W�u�ɓd�������R���_��p���邱�ƂŖ{�i�I�ȃN���[�����[�N���\�ɂȂ�B  �@���̂悤��VP�̐��E�ł̓L�����������^�����邱�Ƃɔ���Ⴕ�ē��@�̎g�p�������Ă��Ă���B���ꂪ�Z�p��Ђ̐V���Ȑ헪�ł���B����͉c�ƓI�Ȑ헪�ł͂Ȃ��A���ǂ���i��n�肽���Ƃ����N���G�[�^�[�B�̒���Ƃ������ق����ǂ����낤�B �@�������u�ۂ�����������ЂƖ�v�Ƃ������Ƃ킴������悤�ɁA���@���g���₷���Ȃ���HDV�ł����Ă��A���܂ł�����͔���ɂ͂Ȃ肦�Ȃ��B��X�͂�������������������Đi�ޕK�v������B���Ď��͂ǂ�Ȃ��̂��o�ꂷ��̂��낤���B �@����������{�X�����Ђ̑�32��u���̃A�C�f�A�������v�R���N�[���̎B�e���n�܂邪�A���N��16�F9���C�h�ɂȂ�A�g�p����L��������HDV��HVR-Z1J�ɂȂ�B�����đ��̃C�x���g�����̂�HVR-Z1J�͍������܂Ńt���ғ��ł���B |
2006�N10��03��(��)
|
�@�u�v�l�u���c�u�c���v�ł���B�ȑO�ɂ����l�̌��������������A��͂��ʂ̐l�ɂ͓���悤���B�����A�������ʂ�����킩��悤�ɗl�X�Ȓm�����������l�������֗��ȃ\�t�g�E�G�A���Љ��Ă���̂Ŏ����Ă݂�Ɨǂ����낤�B �@���͂������������@�Ƃ͈Ⴄ���@�ɂ����WMV��DVD�ɋL�^���Ă���B�g�p������̂̓i�V���i����DVD���R�[�_�[���B������g���ɂ߂ĊȒP��WMV����DVD���쐬���邱�Ƃ��o����B���ݎ��̉�Ђ����̂��������ɍ����ɃL�������}����h�����Ă��邪�A�d���̓{�����e�B�A�̕��X���C���^�[�l�b�g�����p�̋Z�p�w�������S���B���Ԓ��ނ��g����Ă����ڂ̃C���^�[�l�b�g�����p�͎��̉�Ђ�DVD�ɋL�^���Ă���B�\�t�g�E�G�A�ŕϊ�������@�ɔ�ׂ�Ǝ�掿���ቺ���邪�A���A���^�C����MPEG2�ϊ����Ȃ���DVD-R�ɋL�^���邽�ߌ㏈���͕s�v���B�L�^�����Ƃ��Ă͂���ŏ\���ȏ�ł���A�]���ȍ�Ƃ��������D��Ă���Ǝv���B�@�B�͎g�����ɂ���āA�v�҂��Ӑ}�����ȏ�̔\�͂����Ă���邱�Ƃ�����A�����T���o�����Ƃ͋Z�p�n�̐l�Ԃ̊y���݂ł�����B |
2006�N09��28��(��)
|
�@�u�X�g���[�~���O�z�M HTTP ���_�v�Ƃ��������������B�q�b�g���Ă����y�[�W�̓g�b�v���}�C�N���\�t�g�́uWeb �T�[�o�[�X�g���[�~���O �T�[�o�[�v�Ƃ����y�[�W�ŁA�������̉�Ђ́u�X�g���[�~���O�f���̔z�M�v�̃y�[�W���B �@�X�g���[�~���O�z�M�͈�ʓI��RTSP��MMS�Ƃ�������p�̃v���g�R�����g�p���邪�AHTTP�Ƃ���WWW�T�[�o�[�p�̃v���g�R���ł�����z�M���\���B�������X�g���[�~���O��p�̃v���g�R�����g�p����X�g���[�~���O�T�[�o�[�ɂ͐�p�Ƃ��Ă̗��_������B���Ƃ��Έ�ʃ��[�U�[�ɂ͔z�M�����ۑ��ł��Ȃ��Ƃ������Ƃ�A�ړI�̍Đ��ӏ��փX�L�b�v�ł����肷��@�\���B �@����̃L�[���[�h�ɂ��Č����AWEB�T�[�o�[�Ŕz�M����ꍇ�͊����̃C���t���X�g���N�`���𗘗p�o���邱�Ƃ͑傫�ȗ��_���B�X�g���[�~���O�T�[�o�[�Ƃ���Windows Media �T�[�o�[��p����ꍇ��Media�T�[�o�[�\�t�g�E�G�A���C���X�g�[������K�v������B �@�Ȃ��[���X�g���[�~���O�ł����Ă����^�t�@�C�������p���邱�Ƃŗl�X�ȑΉ����ł���悤���B������WWW�T�[�o�[����̃v���O���b�V�u�_�E�����[�h�ł̓N���C�A���g����x�������邱�ƂŃn�[�h�f�B�X�N�ɃL���b�V������A����͂����ɍĐ����n�܂�B����̓_�E�����[�h�o���Ȃ��X�g���[�~���O�Ƃ͐����ŁA���_�ɂ��Ȃ邪�A���_�ł�����B�����AWWW�T�[�o�[��p���ăX�g���[�~���O���s���ƁA�T�[�o�[�̕��ׂ����債�A�����A�N�Z�X���鑽���̃N���C�A���g�̗v�������ɂ͒lj��̃T�[�o�[�n�[�h�E�F�A���K�v�ƂȂ邱�Ƃ������B�܂�꒷��Z�ł���B �@���̉�Ђ��s���Ă��铮��z�M�͂����܂ŏ����̃N���C�A���g�Ɖ��肵�Ă��邽�߁A���݂̂Ƃ����WWW�T�[�o�[�ŊԂɍ����Ă���B��Ђōs���Ă����I���f�}���h�z�M�̃��X�g�ɂ͗l�X�Ȃ��̂�����B���̒��ł��ŋߓ��ɑ����̂������_�̓���T�C�g���B���A���r�f�I�œ���z�M���Ă��邪�A����100�ȏ�̃A�N�Z�X�ł����Ƃ��ς��Ă���B�����čŋߐV�����R���e���c��lj������B  �@��Ђ�WEB�T�[�o�[��svs.ne.jp�����A�����www2.svs.ne.jp����s���Ă���B�ǂ���̃T�[�o�[���C���^�[�l�b�g��100Mbps�Ōq�����Ă���̂ʼn�����x�͖��Ȃ��B���Ƃ̓N���C�A���g���ɂ��T�[�o�[�̕��ׂ����A������16���q����X�g���[�~���O�T�[�o�[�ɐ�ւ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B �@�����ЂƂ̓���z�M�̓��A���^�C���G���R�[�h�ɂ��WEB�������B���ݎ�������������20���قǂ̐ڑ�������B�ڂ����͂���������C�u�G���R�[�h�������������������BWindows Media Player���� http://svs.ne.jp/rt.asx���J���Ă�����������A���^�C���G���R�[�h�̓����24���Ԏ����ł���B�i���X�m�[�g���A���`�E�C���X����������AMicrosoft�A�b�v�f�[�g�����Ă��Đڑ��ł��Ȃ��ꍇ�����邪�j����͂��悢��u�N�ł��ł���ȒP�X�g���[�~���O�v�ɓ˓������悤���B �����ɂ���ăX�^�[�g����܂łɏ������Ԃ�v����ꍇ������B |
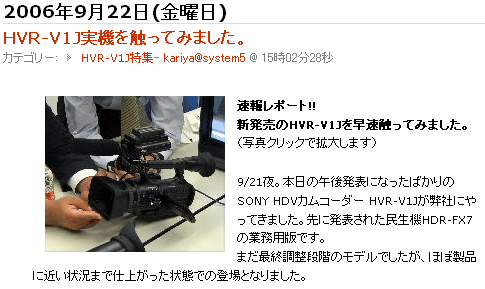 �i���ʐ^���V�X�e���t�@�C�u�̃T�C�g���L���v�`���[�j �@�uhvr-z1j hvr-v1j�v�Ƃ����L�[���[�h���B�ƊE�������������B�������ʂ̓g�b�v���u�V�X�e���t�@�C�u�̃|�[�^���T�C�g�v�Łu�V�X�e���t�@�C�u��HVR-V1J���@���|�[�g�v���q�b�g���Ă����B2�ʂ��u�\�j�[�̕����v3�ʂ��u�S��Ԃ�HVR-V1E(���B���f���j�Љ�̃y�[�W�v������4�ʂ��u�痢�r�f�I�T�[�r�X��HDV��������Ă���y�[�W�v�������B �@���͂܂�HVR-V1J�ɂ͐G��Ă��Ȃ����AHVR-Z1J�ł̎d���ʁA�ғ������l����Ɠ��R�w�����邱�ƂɂȂ낤�B�����ăV�X�e���t�@�C�u��20�N�قǑO�A�����d��Y�Ƃ̃r�f�I���ƕ��̉ے��Ɂu���É��ʼn͖삳��ƌ����Ⴂ�В����撣���Ă��܂��v�ƏЉ��Ĉȗ��̎���ŁA����܂łɂ����X�̉f���@�ނ����[�X��w��������������Ђ��B�������Z1J��HDR���V�X�e���t�@�C�u�ōw�����Ă���B�܂�HVR-V1J���V�X�e���t�@�C�u�Ƃ������ƂɂȂ�B �@���������̌o�̂͑������̂ŁA�����r�f�I���ƕ��̉ے����������������Y�i��������܂����j���͌��݃p�i�\�j�b�NAVC�l�b�g���[�N�X�ЃV�X�e��AV�r�W�l�X���j�b�g���ɂȂ��Ă���B�R�R�ɉ��������̊�ʐ^���f�ڂ���Ă���B���͂��̓������A�����č������������������ōł��M���ł���l�����Ǝv���B�������A���ɏЉ�ꂽ�V�X�e���t�@�C�u�Ń\�j�[���i������w�����Ă���Ƃ����̂͑�ϔ���ł���\����Ȃ����Ƃ��B�������������L��������VARICAM��SDX900�A������DVCPRO HD�ADVCPRO��VTR���g�p���邵�A�ҏW����P2�J���ɑΉ����Ă���B����Ɍ���P2�J���̃L�������������������Ă���B���̂Ƃ��ɂ͎��ɐ��b�ɂȂ邩���m��Ȃ��B �@����HDV�̍��ゾ���A�l�X�Ȑ��i����Ӌ@�킪�����C���i�b�v���ꂽ���Ƃʼnv�X���̎g�p�p�x�͍����Ȃ邾�낤�B�����HDV�͉ƒ�p�ƋƖ��p�A�����p���V�[�����X�Ɍ��ԃt�H�[�}�b�g�Ƃ����邾�낤�B������SD4:3����HD16�F9��HDV�ł̓V�[�����X���B�����m����肱��ɋ߂����̂�DV�����A�ƒ�p��DV�ƋƖ��p��DVCAM/DVCPRO 25�A�����p��DVCPRO 50�͎��Ĕ�Ȃ���̂Ō����ăV�[�����X�ł͂Ȃ������B�����c�O�Ȃ��Ƃ͏�����HDV Format Supporters�ɖ���A�˂Ă��Ȃ����Ƃ��BHDV and HDV logo are trademarks of Sony Corporation and Victor Company of Japan, Limited (JVC).�ł���ɂ�������炸���B�b��̃u���[���CDVD�ł��������^����ƂƂ��Ė���A�˂Ă����킯������A�����͉��������Ɉꔧ�E���ł��炢�������̂��B ���`���̎ʐ^�̓V�X�e���t�@�C�u�̃T�C�g�̃X�N���[���V���b�g�����AV1J��s�\��̍ۂɎg�p�̎|��������Ă����B |
2006�N09��25��(��)
 �@��͂薢����HD��HDV�ւ̕ϊ��ɑΉ������R���o�[�^�[�͔������ꂸ�A�ϊ��ɂ͎��Ԃ�������B���ݎ��̉�Ђł�DVCPRO HD����HDV�ւ̕ϊ���11�{���Ă���HDV�ɏ����o�����߂�MPEG2/TS�t�@�C���ւ̕ϊ���Ƃɑ���Ȏ��Ԃ�v���Ă���B  �@����̎d����HDV���������̃N���C�A���g��HD�f�ނ�����Ō������Ƃ������Ƃ���㗝�X���������̂����AHD��HDV�ւ̕ϊ��ɑΉ������R���o�[�^�[����������Ă��Ȃ������҂����Ȃ̂����m��Ȃ��BDVD���t�����Ɠ��l��1�`2�N�����Ȃ������ɍ�Ɨ�����1/10�ȉ��ɉ����邾�낤�B |
2006�N09��23��(�y)
|
�@�ߍ��͐��I�Ȃ��̂��悭���������B�����L�[���[�h�́u�n���C�[�^�[�@���p�v�������Bhameater�ł͂Ȃ�humeater�ł���B�n���Ƃ͓d���̐ڒn�i�A�[�X�j�ƐM���̊Ԃɐ�����d�ʍ�����N����50Hz�Ȃ���60Hz�̎����I�ȓd���m�C�Y�ŁA�����̏ꍇ�̓u�[���Ƃ����m�C�Y�ɂȂ�A�f���̏ꍇ�͎Ȗ͗l�Ƃ��Č����B �@��X�̎d���ł͉f���𐔕S���[�g�����ꂽ�����������g�킸�L���ő�������A���������B���葤�Ǝ����ʂȓd���n���g���ꍇ�i���g���������ɈقȂ锭�d�@���g����O���p�Ȃǁj�ɂ̓n���ɂ��r�[�g�m�C�Y����������ꍇ������B���������ꍇ�Ɏg�p������̂��n���C�[�^�[���B �A�T�J�͕����p�t�B�[���h�X�C�b�`���[��ASW-100�Ȃǂ�����Ă������[�J�[�ŁA�ƊE�ł͔��ɗL���ȃ��[�J�[���B�n���C�[�^�[�͖ڗ����݂ł͂Ȃ����A���p����ł́u���̉��̗͎����v�I���݂Ƃ��ďd�v�ȃA�C�e���ł���B���Ȃ݂Ɏ��̓{�����X�n����D����HAMEATER�ł���B�I���W�I |
2006�N09��22��(��)
|
�@�u�����p�t�B�[���h���j�^�[�v�ł̌����������B17��8�猏���̃g�b�v�Łu�痢�r�f�I���g�p����B�e�@�ނɂ����v�y�[�W���q�b�g���Ă����B �@�ߍ��͉t�����j�^�[�̐��\���ǂ��Ȃ�A�t�B�[���h�ł��t�����j�^�[���g����悤�ɂȂ������A�ǂ��炩�ƌ����n�C�r�W�����̎��^���Ɍ��肳���悤���B�\�j�[����LMD-9050�Ƃ������D�ꂽ�t�����j�^�[��LUMA�V���[�Y�Ƃ��Ĕ�������A�����ɂ���܂ł̃u���E���ǎ��̃t�B�[���h���j�^�[�͐��Y�����ƂȂ��Ă��܂����B������SD���^�̌���ł͍��Ȃ��u���E���ǎ��̃��j�^�[�����߂�ē������B��͂�SD�ƃu���E���ǂ̑����͉t���Ƃ͈Ⴄ�B �@�n�C�r�W�����t���e���r�ŏ]���̃A�i���O���������ĉ掿�̈����ɜ��R�Ƃ��ꂽ�����������낤�B���Ƀn�C�r�W������DVD��n�[�h�f�B�X�N�Ƀ_�E���R���o�[�g�L�^�����Ƃ��ɂ��̃V���b�N�͑傫���悤���B�u����Ȃ͂�����Ȃ������v�ƌ����킯�ł���B�����������l�͌��𑵂��āu�����u���E���ǃe���r�Ō�����������ۂǂ��ꂢ�v�ƌ�����B����������͂܂���������������B�����𑜓x1080�{�̃n�C�r�W�����ɍœK�����ꂽ�t�����j�^�[�Ő����𑜓x480�{��SD����������Γ��R�����Ȃ�B���Ƃ���17�D�t�����j�^�[���ڑ����ꂽ�p�\�R���̃��j�^�[�ݒ��1280�~1024����1024�~768�ɕς����ꍇ�̓p�\�R���̉𑜓x�ƃ��j�^�[�̉𑜓x�i�s�N�Z�����j����v���Ȃ����ߕ����Ȃǂ̓{�P�Ă��܂��B���������̏�Ԃ�1024�~768�ɍœK�����ꂽ15�D�t����ڑ�����ɂ߂Ă��ꂢ�ȉ�ʂɂȂ�B �@�������Ƃ��u���E���ǂōs�����ꍇ�͂����͂Ȃ�Ȃ��B�u���E���ǂ̏ꍇ�͌u���ʂɃh�b�g�������A�D�݂̉𑜓x��ݒ肷�邱�Ƃ��o����B�ŋ߂̕����p�t�����j�^�[�ł͗l�X�ȋZ�p�ɂ���Ă��Ȃ�SD�ł̉掿�͌��サ�����A��͂�HD�ɍœK�����邱�Ƃ�SD�͋]���ɂ�����Ȃ��B �@���̉�Ђ��g���Ă���SD�t�B�[���h���j�^�[�̓\�j�[��BVM-9045QD��PVM-9045Q�APVM-9044Q�APVM-6041Q���B�Ɩ��p��PVM�V���[�Y���f���m�F�p���j�^�[�ł���̂ɑ��A�����p�͉摜�]���p���j�^�[�Ɉʒu�t�����A�}�X���j�ɏ��������̂ɂȂ�B������\��PVM�V���[�Y������ɂȂ邪�A���i�������Ȃ�B9�D�̕Ȃɉƒ�p��37�C���`�t���n�C�r�W�����e���r�Ɠ������炢�Ƃ����Ό������t�����낤�B�ʐς�����̒P����37�C���`�t���e���r��15�{�قǂɂȂ�B�������A37�C���`�t���e���r�ł��ꂢ�Ɍ�����f�����B�e���邽�߂ɂ͂����������t�B�[���h���j�^�[���K�v�ɂȂ�B �@�ʐ^��BVM-9045QD��16�F9�̃J���[�o�[���A���_�[�X�L�������[�h�ŕ\�����������̂��BAQUOS���A���_�[�X�L������W���������A�l�b�g�z�M��DVD�̃p�\�R���ł̎������l����ƍ���͏]���̃I�[�o�[�X�L�����ł͂Ȃ��A�A���_�[�X�L�������W���ɂȂ邩������Ȃ��B |
2006�N09��21��(��)
 �@�u�Ɩ� �_�r���O �V�X�e���v�������B�����ē���IP���烄�t�[�Łu�Ɩ��p �_�r���O�V�X�e���v�ƃO�[�O���Łu�Ɩ��p �_�r���O�V�X�e���v�ł���������Ă����B�������ʂ����̉�Ђ����ЂŕۗL����_�r���O�V�X�e���̃y�[�W���B �@���̉�Ђł�VHS�ւ̃_�r���O�͎ʐ^�̃V�X�e���ōs���Ă���BVP�Ȃǂ�VHS�R�s�[�ł͂��̃V�X�e���ł�400�{�^�����x�̏����\�͂������Ă���B�Ƃ����Ă�120������1000�{�I�[�_�[�ȂǁA�����\�͂��ǂ����Ȃ��ꍇ�͎��C����p�̃~���[�}�U�[���쐬���A�S���\�{�̑��x�Ńp���P�[�L�i���ڃ��[���̐��e�[�v�j�Ƀv�����g���邱�ƂɂȂ�B����������Ƃ͋��͍H��ōs�����Ƃɂ���B�������ŋ߂ł�VHS����DVD�ł̔[�i�������Ȃ����BDVD�͑�ʂ̏ꍇ�̓v���X���A���ʂ̏ꍇ��DVD-R�R�s�[�ɂȂ�B��͂莞��̕ω����낤�B���ł̓e���r���n�[�h�f�B�X�N�Ř^�悵�A���̃R�s�[��DVD-R�ɕۑ�����̂����ʂɂȂ��Ă����BVHS���I�[�f�B�I�J�Z�b�g�e�[�v�Ɠ��l�̉^����H��n�߂��B �@�n��g�A�i���O�������I�����鎞�܂ŁA�Ȃ�Ƃ��ێ��ł�����̃V�X�e�����剝���Ƃ������ƂɂȂ�B�����A�ʂ�����VHS�͂��̐�����p�������̂��낤���H���ݎ��̉�ЂŕۗL���Ă��鋌�t�H�[�}�b�g��VHS�ȑO��1/2�D�I�[�v�����[����3/4�DU�}�`�b�N�A�����ă��T�A���U�A���V�A���TSHB�AHi8�AM�U�A���J���A1�DC�t�H�[�}�b�g�Ȃǂ��B�����͍����_�r���O�˗�������B���RVHS��S-VHS����̃_�r���O�͍���10�N�ȏ�͕K�v���낤�B �@�ŋߑ����̂�VHS����A8�~���r�f�I�����DVD�����B�܂�ƒ���Ђ̉f�����Y���f�W�^�������ĉi�v�ۑ����l�������ʂł���B�m���ɈȑO�̍L���Ȃǂł́u���i�v�I�v��u�i�v�ۑ��v�Ƃ������t���g���Ă����B���Ȃ݂�Google�ŁuDVD �i�v�ۑ��v�����������1,140,000�����q�b�g����B����������͊Ԉ���Ă���B�����i�v�ۑ����l���Ă���̂ł����DVD�����I�Ƀo�b�N�A�b�v���A�X�V���Ă䂩�˂Ȃ�Ȃ��B����ɉ\�Ȃ�I���W�i���e�[�v���ۑ����ׂ����낤�B���̂Ȃ�DVD��CD�̂悤�Ȍ��f�B�X�N�͉i�v�ǂ��납�A���i�v�I�Ƃ������Ȃ��̂��BDVD�̕ۑ����ɂ��Ă͎��̉�Ђ�DVD�̃y�[�W��Q&A���Q�l�ɂ��Ă��炢�����B�܂���a�����̃R�����ŏ��Z�p�������̏���n�������I�m�Ȉӌ����q�ׂ��Ă���B �@DVD�Ƃ͌����ď����Ȃ����̂ł͂Ȃ��B�n�[�h�f�B�X�N�Ɠ��l�A����ʂɋL�^���ꂽ�y���ȏ��Ȃ̂��B |
2006�N09��17��(��)
|
�@�u�N���[�� �V���b�g �B�e�v�������B��������Ă����̂́uHDV�L���������g��������y���@�B�e�v���B �@�N���[���V���b�g�Ƃ͎B�e�Z�p�̈�����A�Y�[����p���ƈقȂ�A�L���������㉺�A���E�Ɉړ����Ȃ���B�邱�Ƃ��B�~�j�W�u��N���[���A���[����p�����B�e�͊�ƃr�f�I�̐���ł͗\�Z�������邽�߂ɂȂ��Ȃ����p���ɂ������A��p�������邾���̌��ʂ͂���B�X�^�W�I�B��̃h���}�ł̓N���[����f�X�^������݂���Ă���̂ŃN���[���V���b�g�͎��R�Ɏg���邪�A�I�[�v�����P�ł͓��@����ނ��߂ɁA���R�����K�v�ȃJ�b�g�݂̂ɃN���[�����g����B�������A�ŋߗ��s�̊ؗ��h���}�ł͕p�ɂɃN���[����[�����g���Ă���悤���B���̂��������Ⴄ�̂��낤���B�f��̂悤�ɑ������傫���Ȃ�ƃN���[����[���͓�����O�ɂȂ邪�A����ł��G���f�B���O�����ɃN���[�����g���Ă����i������B��͂�\�Z�Ƃ������Ƃ��B �@�Ƃ��낪�ŋ߂ł͏��^HD�L�������p�Ƀ����O�T�C�Y�W�u+�����[�g�_��Ȃǂ��o�ꂵ�A�N���[���V���b�g�������ȒP�ɂȂ����B���̉�Ђł��~���[�̃v���W�u���~�J�~�̃����R���_���ۗL���A��y�ȃN���[���V���b�g�ɑΉ����Ă���B�N���[���V���b�g�𗘗p�������ꃌ�|�[�g�ɂ͎��̂悤�Ȃ��̂��z�[���y�[�W�Ō��J���Ă���B�ʐ^���N���b�N���Ă��������ƊY���y�[�W���V�����E�C���h�E�ŊJ���B  �S�X�y���V���K�[�u���`���[�h�E�n�[�g���C�v��PV�B�e 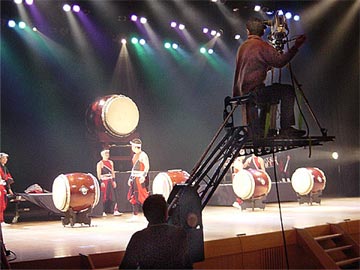 �a���ہu�������g�v�̔̔��p�r�f�I�B�e���� �f�������C�h�����A���f��ɋ߂���p�ɂȂ�ƁA�L���������[�N���f��Ɠ������̂��K�v�ɂȂ�B�r�f�I�ɃN���[���V���b�g���ǂ��������ɗ��p����邩�́A�Z�p��Љ]�X�Ƃ��������ē������ł���B |
2006�N09��14��(��)
�@�����L�[���[�h�́u���ׂĂ͎B�e�����v�ł���B�u���ׂĂ͎B�e����n�܂�v�Ƃ����͎̂��̉�Ђ̃��b�g�[�ł���A�e�[�}���B��������Ă������ʂɁu�����ɉ�����»�c�����Y�̖����Ȑ��E�v�������N�W���������B�c�����Y���Ɩʎ��͖������u�ǂ݉����̂���y�[�W�Ȃ̂Ń����N�v�ȂǂƏ������Ɓu�K�i�P�c�j�̌����y���Ȃ�v�Ƃ������̂��B�����Ĉ����C�͂��Ȃ����A�撣��˂Ǝv���B �@������ɂ��Ă����ʂƂ����d���͖����Ȃ�Ȃ��͂����B���ꂪ��X�Z�p��Ђ̐��Ƃł���g���ł���͂����B������u���ׂĂ͎B�e����n�܂�v�͕ς��Ȃ��e�[�}�ł��葱���邾�낤�B�u�B�e�Z�p�̌���v�͉�X�ɂƂ��čő�̖ڕW�ł���B |
2006�N09��10��(��)
�@�udxc-�����Y�v�Ƃ��������BDXC�Ƃ̓\�j�[�̋Ɩ��p�L�������ɕt���i�ԂŁA�����p�ɂ�BVP��BVW�AHDW���̕i�Ԃ��t���B�Ɩ��p�ł�DXC�̂ق�DSR�APDW�Ȃǂ̕i�Ԃ��g����B  ���iDXC-637��J20�~8���j �@�������e���r�L�������͑������郌���Y�ɂ���ĉ掿�ɑ傫���Ⴂ���o��B�Ɩ��p�̃����Y�i�L���m���̏ꍇ��YJ�V���[�Y�j�͕����p��J�V���[�Y��HJ�V���[�Y�Ɣ�ׂĊm���ɉ𑜓x���Ⴂ�B�����Y�̈Ⴂ�������p�L�������ƋƖ��p�L�������̉掿�����߂Ă���Ƃ����Ă��ߌ��ł͂���܂��B����Ɏg�p���i�̊W���낤���A�Y�[����t�H�[�J�X�̓����ɂ����炩�ȍ�������B �@������̂̎B�e�ł͋Ɩ��p�L�������ł����Ă������p�����Y���g�p����B���R�͉𑜓x�̍����ƁA�Y�[���̔S����J�����}���̍D�݂ɍ��킹�ă��[�J�[��SC�Œ������Ă��炦�邩�炾�BYJ�V���[�Y�̏ꍇ���[�J�͂����������Ή������Ă��Ȃ��炵���B�����������������ƂƁA�蓮�Y�[�����g���l�����Ȃ����Ƃɂ����̂Ǝv����B  ���i�ʐ^��DXC-637��J14�~8.5���j �@�����̃L�������}���ɂ͓d���Y�[�����g�p����l���������A���ł͓d�C�͒p�Ƃ����X��������B�E�l�Z�Ƃ��Ă̎蓮�Y�[���������v�������̂��B���͂��̂��Ƃɂ͍S�炸�A�K�v�Ƃ�����I�C���_���v�Y�[�}�[�Ȃǂ��g�����AHDV�̃L�������ł�A�n�_�`B�n�_�ŃY�[���A�t�H�[�J�X�A�A�C���X��ݒ肵�A�����œ����I�[�g�g�����W�V�������g�p����B�����������܂Ŋ�{�͎蓮���B�蓮�Y�[�����ӂ̂܂܂ɏo���Ȃ���Έ�l�O�Ƃ͌����Ȃ��B�B�e����Ńx�e�����̊ē���{�ɖ����L���������[�N��v�����邱�Ƃ�����B�u���̂������̃X���[�Y�[���ŁA�t�H�[�J�X�t�H���[�ˁv�ł���B�����炭�ҏW�ł͎g��Ȃ��J�b�g�����A�ē̂���]�ʂ�Ƀe�[�N�𑝂₷�B���̎��d�C�ɐ�ւ��Ă͂����Ȃ��B�v����ɘr�����ł���B |
2006�N09��07��(��)
 TBS�̐���f�X�N����d�b���������B�����������̋}�ȎB�e���B�d�b���I���ăA�N�Z�X�ׂĂ݂�ƁuBVW-D600�v�u�x�[�J�� �B�e ����v�Ȃǂ��������BIP�������TBS�̔ԑg�𐧍삵�Ă����Ђ���̌����L�[���[�h�ł���B���ǂ��̌���͍�粂��S�����邱�ƂɂȂ����B TBS�̐���f�X�N����d�b���������B�����������̋}�ȎB�e���B�d�b���I���ăA�N�Z�X�ׂĂ݂�ƁuBVW-D600�v�u�x�[�J�� �B�e ����v�Ȃǂ��������BIP�������TBS�̔ԑg�𐧍삵�Ă����Ђ���̌����L�[���[�h�ł���B���ǂ��̌���͍�粂��S�����邱�ƂɂȂ����B�@DVCAM��DVCPRO�AHDCAM���嗬�ɂȂ��Ă��邪�A���Ȃ��x�[�J�����݂ł���B��͂�2011�N�܂ł̓x�[�^�[�J���̃I�L�T�C�h�i���^����SP�ł͖����I�L�T�C�h�ł���j�͎c���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���N�͔ԑg�̎d���������Ă���B��X�̂悤�ȃv���_�N�V�����ł��l�b�g�̂��A�ŗl�X�Ȉ�������������B�B�e�͊�Ƃ̃T�C�Y�ł͂Ȃ��A�L�������}���̊����A�Z�p�A�����������̂��ƍl����B �@�Ԃ��Ȃ��u�̂��������ɍ��́v���n�܂�B���̉�Ђ�����n�C�r�W�������X�^�W�I�B�e�ō�粂��M������l�N�ɒ��p�Ő�]���Ă��炤���Ƃɂ����B  |
2006�N09��04��(��)
�@�uHDV�Ŏc���v�Ƃ����L�[���[�h���B�ŋ߂�VP�B�e�ł̓�CAM��DVCAM�ŋL�^�������HDV�ŋL�^���邱�Ƃ������Ȃ����BSD�Ō���Ȃ����掿��]�ޏꍇ�̓f�W�^���x�[�J����IKEGAM��D45��J14�~8�Ƃ����ƂĂ��������傫���d��EFP�p�����Y���g�p���ĎB�e���邪�A2011�N�̃A�i���O�n��g�����̒�g��Ƃ��ăR�X�g�̒ႢHVR-Z1J�Ńn�C�r�W�����B�e���s���Ă���B�������HDCAM�ŎB�e���邱�Ƃ͗��z�����A���VP�͗\�Z�����Ă̂��̂�����HDV�t�H�[�}�b�g�͗L�肪�����B  |
| �O�� | ���� |
�@
PHOTOHITO�u���O�p�[�c
|
�j�b�N�l�[���FSENRI �s���{���F���E���{ �f������/�B�e�Z�p��� (���j�痢�r�f�I�T�[�r�X ��\������� �k�����x�����q���b�eHP�̊Ǘ��l�ł��B��낵�����肢���܂��B ���F�X�o�܂��� »���킵������ �o�C�I�O���t�B�[ |